離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
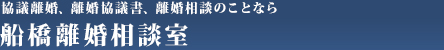
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
|---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらへ
夫婦の一方に主な離婚原因があるとき
離婚の慰謝料
離婚に至った主な原因が夫婦のいずれか一方にあるときは、その原因をつくった者は配偶者に慰謝料を支払う法律上の義務を負います。
離婚に伴う慰謝料の額は夫婦ごとに異なり、そして支払い額の幅も大きくあります。
協議離婚では夫婦で話し合って慰謝料の支払い額を決めることが普通です。
なお、不貞行為が離婚の原因になっているときは、不貞行為の当事者である不倫した配偶者の相手方にも不貞行為(不法行為)を原因とした慰謝料の支払い義務が生じます。
離婚に伴う慰謝料の支払い

離婚に至った理由は夫婦ごとに様々です。
多く聞かれるのが「性格の不一致」ですが、そのほかに不倫、暴力行為、多額の借金など、夫婦の一方側に明らかに離婚となった原因のある場合があります。
離婚しなくても、不倫や暴力行為は、法律上において配偶者の権利を侵害する不法行為となります。
さらに、不法行為が原因となって希望していなかった離婚に至ることになれば、その権利侵害は重大であると考えられます。
こうした不法行為を原因とした離婚では、離婚の原因がある側から他方側に対して離婚に伴う慰謝料が支払われることになります。
協議離婚においては、夫婦の話し合いで慰謝料の支払い額などを取り決めます。
もし、夫婦の話し合いで離婚の慰謝料支払いについて解決ができないときは、家庭裁判所での調停または訴訟によって慰謝料を請求することもできます。
ただし、協議離婚することを選択する夫婦の多くは、解決までに長い期間を要するうえに弁護士費用の負担が重くかかる訴訟をしなくて済むように、できる限り夫婦の協議で解決しようと努めます。
離婚に関する慰謝料は、離婚の届出までにしなくても、離婚の成立から3年以内であれば消滅時効にかからず、法律上で慰謝料を請求することが認められます。
ただし、離婚後における慰謝料の請求では、話し合いによる解決が容易でない状況にあることが多く見られます。
離婚の成立で夫婦の関係が解消してしまうと、離婚に向けて協力するという目的がなくなり、慰謝料を請求する側と慰謝料を請求される側とに明確に立場が分かれます。
離婚に向けて条件を整理するなかで慰謝料を話し合うという機会がなくなり、後追い的な金銭の請求になりますので、どうしても交渉は厳しくなってしまいます。
話し合いで慰謝料について解決できなければ、訴訟になり、費用面の負担も生じます。
また、訴訟する前提として、不法行為の事実を証明する証拠資料も必要になります。
離婚の成立後に慰謝料を請求することを考えるのであれば、裁判を起こした場合の見通し、弁護士へ支払う報酬等費用の見込み額を事前に弁護士へ確認しておくことをお勧めします。
不倫を原因とした離婚では、配偶者の不倫相手に対する慰謝料の請求も可能になりますので、全体の見通しを踏まえて請求の手続をすすめることも大切になります。
なお、離婚の理由として多く聞かれる「性格の不一致」は、夫婦の双方に原因があるとみなされるため、慰謝料の請求は一般には難しいと考えられます。
慰謝料の相場額
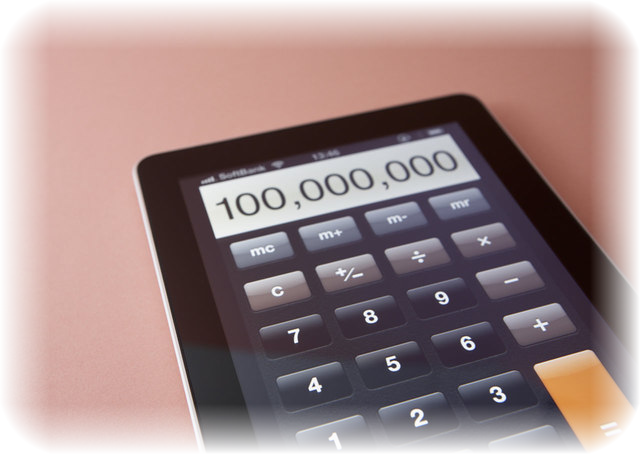
離婚の慰謝料は一律的な評価額の算出式がないため、協議離婚では夫婦の話し合いによって慰謝料額などの支払い条件を決めています。
一般には数十万円から500万円の範囲内で慰謝料額が定められ、中心帯は200万から300万円になるとされており、これが離婚慰謝料の相場と言われています。
離婚の慰謝料は、相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、いくらでも請求することは自由です。
実務上では、離婚に責任のない被害者側が受けた精神的及び身体的な苦痛の大きさ、離婚に責任のある側の支払い能力などを踏まえて、慰謝料の額を決めていきます。
実際に協議離婚で慰謝料を定めている夫婦の事例を見ていますと、理論によるのではなく、慰謝料を請求する側と支払い側の話し合い状況で決まっているようです。
離婚することで受けた精神的苦痛が大きいと考える方は高い慰謝料額を請求し、その支払いを求める話し合いに時間を惜しまず、最終的に希望に近い額で合意に至ってます。
早く離婚することを優先する方は、慰謝料を放棄して離婚の合意をすることもあります。
こうした状況は、裁判所が関与しない協議離婚であるから可能になるのでしょう。
なお、裁判所の実務では、離婚原因のない側の精神的被害の大きさ、婚姻期間、未成熟子の有無、双方の年齢・収入資産などを考慮して慰謝料の額が決められています。
慰謝料の内訳
離婚の慰謝料は、不法行為による損害賠償金という性質の金銭です。
離婚における慰謝料は、大きく2つに区分して考えることができます。ただし、実務上ではこのような区分をして支払うことはありません。
〔慰謝料の内訳〕
- 離婚原因の慰謝料-不貞行為、暴力行為などで受けた精神的苦痛
- 離婚することの慰謝料-希望していない離婚をすることで受けた精神的苦痛
慰謝料の難しさ
離婚協議において慰謝料の支払い、その条件を定めることは容易でない面もあります。
どちらか一方が離婚原因のある有責配偶者になることで慰謝料の支払い義務が発生しますが、離婚の慰謝料は高額であることから、負担者側にも大きな負担となります。
お互いに離婚になった原因は相手方にあると考えていることもあり、話し合いをしても慰謝料については平行線になることもあります。
離婚になった責任を認めることで慰謝料の負担が生じることを避けたいとの意向も働きます。
こうしたこともあり、事実を確認できる不貞行為など、明らかな不法行為がないなかでの離婚協議では、慰謝料の話は慎重に進められます。
慰謝料の支払い方法
離婚の慰謝料は不法行為に基づく損害賠償であるため、離婚の成立にあわせて一括して支払うことが原則的な考え方になります。
財産分与の対象となる預貯金などの金融資産があったり、夫婦共同財産の住宅を売却するときには、そうした財産分与の配分額を慰謝料の支払いに充当することもできます。
しかし、現実には離婚の慰謝料は高額となり、財産分与ではカバーすることができないとき、離婚した後に分割払いで支払うことになります。
分割払いは途中で滞納が生じたり、支払いが止まってしまうリスクがあることから、離婚時に慰謝料の支払いほかの離婚条件も含めて離婚協議書を作成します。
慰謝料の分割払いとなる額が大きいときは、支払いの安全を高めるために、公正証書で慰謝料の支払いを含めて離婚契約を結ぶことがあります。
養育費での調整
上記のように離婚の慰謝料を財産分与の形で調整することは一般に行われていることですが、慰謝料見合いの分を養育費の月額に上乗せをする方も見られます。
養育費の月額を父母の間で決めることに制限はありませんが、このような方法をとることには注意が必要になります。
経済的に自立できない未成熟子の監護養育にかかる費用を父母で分担するために支払うものが養育費になりますが、養育費は父母の収入変動、再婚などで増減する余地があるものです。
たとえば、養育費を受領する側が再婚をして、再婚相手と子どもを養子縁組させると、家庭裁判への申し立てによって養育費の支払いが免除される可能性が高いと言えます。
そうなると養育費の支払いがなくなり、同時に慰謝料の受け取りも終了することになります。
このように養育費は財産分与と異なり、離婚時に契約してもその後の事情の変更によって減免される可能性のあることに注意が必要です。
不倫相手への慰謝料請求
配偶者の不倫(不貞行為)が原因で離婚になる場合、その不倫相手に不法行為のあったことが認められると、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
不倫は共同不法行為となるため、慰謝料を請求する側は、配偶者と不倫相手の両方に対して、慰謝料の額を分けて請求することができます。
また、二人のどちらか一方側だけに慰謝料を請求することも可能です。
不倫相手への慰謝料請求は、配偶者の不倫相手が誰であったかを調査等により特定し、不倫に関する証拠資料をある程度は揃えたうえで手続きをすすめることが安全です。
不倫相手が不倫の事実をすぐに認めることもありますので、そのようなときは不倫の証拠資料も必要とならずに、不倫慰謝料を受け取ることも可能になります。
当事者同士で連絡を取り合って不倫の問題解決に向けて話し合うこともできますが、はじめに慰謝料請求する内容証明郵便を送付することが一般に行われています。
なお、婚姻の破綻した後において起きた男女関係は、その行為が婚姻を壊すものにならないという理由から、損害賠償請求をしても認められないとされています。
また、不倫相手に対して慰謝料請求するには、不倫の事実と相手を知ってから3年以内に請求しなければ、消滅時効の成立によって慰謝料請求しても支払いを拒否されることもあります。最後に不倫が行われてから20年を経過したときも同様です。
不倫相手に慰謝料請求する
不倫浮気の調査費用

「プライバシーが確保されていますので、落ち着いてご相談いただけます。」
協議離婚など家事専門の行政書士事務所
平日はお仕事で忙しい方も多いため、土日も事務所を開けています。お電話、メールによる対応のほか、ご来所によるお打合せもできます。※ご来所は予約制です。
事務所概要とアクセス
離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
- 離婚協議書
- 離婚条件を定める公正証書
- (別居時における)婚姻費用の分担契約
- 夫婦間の誓約書
- 不倫問題に対応する示談書
- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
離婚協議書作成サポートのお申し込み

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
事務所のご案内
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

運営元
船橋つかだ行政書士事務所
住所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
アクセス
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋駅から徒歩4分
ごあいさつ

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
ご利用者様の声175名
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)
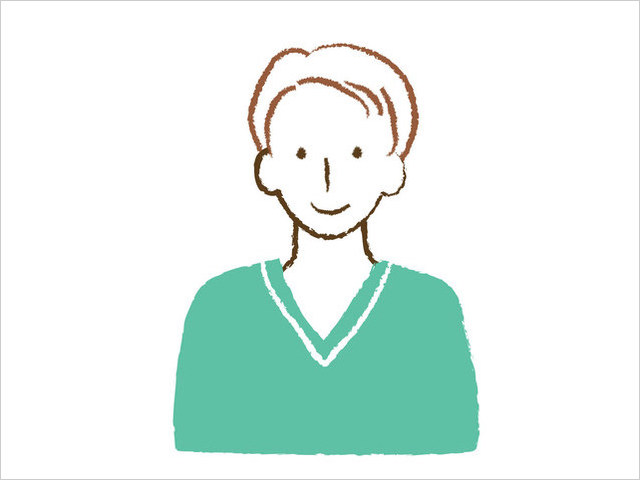
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)
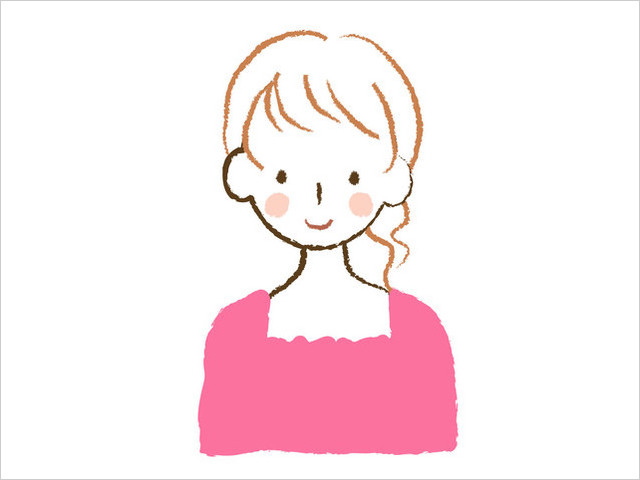
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
