離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
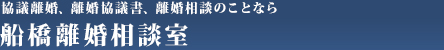
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
|---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらへ
婚姻期間に夫婦で共同形成した財産の清算など
財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築き上げた財産は、離婚時に財産分与として分割、清算されます。
夫婦の共同財産は二人で平等に原則として半分づつ分けるという考え方(2分の1ルール)が存在しますが、それにとらわれず夫婦の合意で財産分割の割合などを自由に定められます。
財産分与では、共同財産を清算する要素のほか、離婚原因に関する慰謝料、収入が十分にない配偶者側に対する扶養的配分(生活費を補助する支払い)も含めることができます。
主に財産分与には3つの要素があります。
「財産分与」の要素とは?
- 清算(夫婦の共同財産を分割、清算する)
- 慰謝料(離婚の原因に対する慰謝料を考慮する)
- 扶養(離婚後の生活に対する扶養補助)
財産分与の対象・目的

原則として、婚姻していた期間(別居期間を除く)に夫婦で築いた財産が財産分与の対象となります。
預貯金、不動産、自動車、株式、保険、退職金などが主な対象財産になります。
離婚の時点で夫婦のどちら側の名義であるかにかかわらず、実質的に共同財産であると認められる財産は、財産分与の対象になります。
ただし、夫婦が所有する財産でも、それぞれが結婚前から所有していた財産、親などから相続又は贈与で譲り受けた財産は、夫婦で協力して築いた財産ではありませんので、財産分与の対象から外します。
こうした財産分与の対象にならない財産を「特有財産(とくゆうざいさん)」といいます。
預貯金などの流動資産が多くあれば、財産の半分が行ない易くて財産分与の合意はスムーズになり、離婚後における双方の生活に経済的な不安もありません。
しかし、主な財産は不動産だけである事例も多くあり、こうしたときの財産分与では対応面で難しいことにもなります。
不動産の財産分与は、その不動産の購入時に利用した住宅ローンの整理方法と離婚後の使用がポイントになります。
住宅ローンの支払いが残っていても不動産の時価評価額より住宅ローンの残債が少なければ、財産分与として精算が可能です。
ところが、時価評価額より住宅ローンの残債が多くなっているとき(「オーバーローン住宅」といいます)は、一般に対応が難しくなります。
オーバーローン住宅であれば、その不動産の財産評価がマイナスになってしまうため、ほかに財産が無ければ、財産分与が困難になります。
そして、不動産の財産分与を考えるとき、夫婦の一方が離婚後も不動産に居住するかどうかという点も、整理上でポイントになります。
そこに住み続けるのであれば、二人のいずれかが住宅ローンを返済していくことになります。
そこで、住宅ローンの返済者を決めなければなりませんが、住宅ローンの残債、離婚後の住宅居住者、それぞれの収入、未成熟子の有無などを踏まえて判断することになります。
なお、財産分与を考える中では、慰謝料を含めることも行なわれています。
慰謝料だけを単独で定めることは、見栄えが良くないという理由から避ける向きもあります。
しかし、財産分与の名目で定めるのであれば、外観上できれいに映るということです。
こうして慰謝料を財産分与に含めるときには、財産分与のほかに慰謝料を請求しない旨を離婚協議書(公正証書)で確認しておくことが必要になります。
そうした確認をしておかないと、離婚後に慰謝料の請求が起きる可能性を残してしまいます。
このほか、夫婦一方が離婚後の収入が十分にないことが見込まれる場合、その側に財産分与を多く配分することで経済面で生活を安定させることが行なわれます。
このような財産分与を「扶養的財産分与」と言いますが、どの離婚においても扶養的財産分与が行なわれる訳ではありません。
清算的財産分与や慰謝料だけでは離婚後の生活資金として不足し、一方に他方を扶養の補助をできるだけの資力がある場合になります。
扶養的財産分与は、離婚時に一時金を払う対応でも可能ですが、毎月の定期金で支払うことが一般には見られます。
また、扶養的財産分与の支払いを長期とすることも可能ですが、一般には数年であり、3年位が多く見られます。
なお、扶養的財産分与は離婚後の補助的な扶養となりますので、婚姻中における婚姻費用のような高水準の給付額とはなりません。
財産分与の金額は、夫婦の話し合いで離婚条件の全体を踏まえて決められることになります。
離婚または別居時が基準になります
財産分与は、婚姻していた期間に夫婦が協力して築いた財産の清算が主な目的になります。
財産分与の対象となる財産は、形式上の名義の如何に関わりなく、夫婦の協力で一緒に形成してきた実質的な共同財産になります。
この財産分与の対象財産を、いつの時点において確定するかという問題があります。
夫婦が離婚するまでに別居の期間が入ることが少なくありません。
別居から離婚までの期間が長くになれば、その間に形成される財産も小さな額ではなくなり、財産分与の対象に含めるか否かで結果に違いがでてきます。
別居開始後に形成された財産は夫婦の共同財産にならないと実務上では整理されています。
つまり、婚姻期間をそのまま対象とするのではなく、別居を開始した時点における財産を分与対象の財産とします。
別居時点とするか離婚時点とするかには、それぞれの考え方があります。実際には、別居時を基準としたうえで、別居期間も事情によって調整することもあり得ることになります。
なお、財産分与の考える時点における財産をすべて双方が把握していないこともあります。
お互いに誠意をもって情報を開示すれば問題ありませんが、一方側が財産を管理している場合には他方には財産が不明であることもあります。
もし、財産分与を定めるときに財産を隠していたときは、隠していた財産が見付かったときには、その財産についても分与することになります。
財産分与に関しては「2分の1ルール」がありますが、夫婦双方が納得できる形で決めることが大切になります。
退職金の扱い
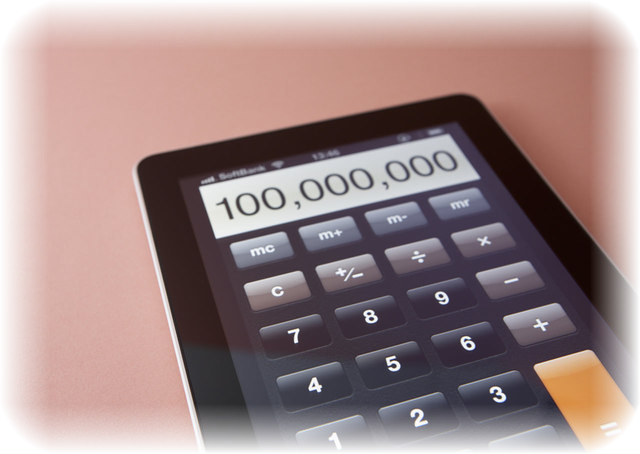
給与所得者にとって退職金は大きな財産となります。
退職金には給与の後払い的な性格もあるため、離婚時の財産分与の対象になります。
しかし、離婚するまでには退職金の支払い時期が到来しないことから、退職金を財産分与でどう扱うかが問題となります。
離婚協議を始める時点で、会社員や公務員であって、数年後には定年を迎えて退職金を受け取ることが予定されている場合があります。
経済情勢によっては定年退職する前に企業が倒産してしまうことや、リストラの実施によって定年前に退職することも考えられます。
そのため、離婚から定年退職の予定時期までの期間を考慮して、退職金を財産分与の対象とするか否か、どのように配分するかを検討します。
明確となる退職金の配分計算の基準はなく、各ケースごとに考えて判断します。
定年退職するまで勤務期間が短いほど、また、会社員よりも公務員である方が退職金を受け取る可能性が高いと言えます。
財産分与の対象とする退職金の額は、離婚時に自己都合退職する前提で計算したり、定年退職時の予定額を婚姻期間で按分して計算する方法もあります。
財産分与での支払方法は、離婚時の計算額で一括払いできれば良いのですが、義務者側に預貯金が少なかったり、退職金の額が大きいときは、退職金の支給時に支払うことで取り決めることもあります。
将来に退職金を支払う約束するときは、離婚条件を公正証書契約にしておくと安心です。
もうすぐ離婚する予定です。夫はあと5年程で会社を定年退職する予定になっています。このように退職時期が近い場合は、退職金も財産分与の対象になると聞きました。わたしの場合にも、財産分与の対象となるのでしょうか?
5年ぐらい先の退職であれば、退職金を財産分与に含めることも可能であると考えます。退職金の支給予定額を確認して、婚姻期間に相当する分について財産分与するように決めることもできます。金額、支払時期について、夫婦間で明確にしておきます。
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に一緒につくってきた財産が対象になります。住宅のほか、預貯金、生命保険、株式、自動車などが財産分与の対象になります。
このほかに退職金も、財産分与の対象になることがあります。退職金は給与の後払いの性格を有すると考えられているためです。
退職金は退職時に支給されるため、退職金が確実に支給される保証はありません。
また、その支給額も、退職金規程が変更されることなどで変わります。
確定していない退職金であるため、財産分与へ含めるときの給付条件を定める方法は、個別の事情を踏まえて定めます。
退職金は、懲戒免職、倒産など、最悪のときには全く支給されないこともあります。
このため、退職金の配分額をいつ支払うかという問題があります。本来であれば、財産分与として離婚時に清算することが考えられます。
しかし、現実にはまだ退職金が払われていませんので、ほとんどのケースでは一括払いで離婚時に清算できません。
そうかといって退職金の支給時とすれば、だいぶ先になってしまうため、約束どおりに財産分与として本当に支払われるのか心配になります。
このようなときは、公正証書による契約をすることが考えられます。
また、退職金の財産分与の額を、どう定めるかという問題があります。
離婚時の支給試算額をもとに決める方法もあります。そのほか、将来に支給された退職金の割合で決める方法もあります。
このような方法の違いによって、財産分与の額も異なってきます。
退職金を財産分与に含めることが可能なときも、その金額、支払方法をどのように定めるか、夫婦での話し合いが必要になります。
手続きが面倒でも退職金は大きな額となりますので、財産分与の対象に含める合意ができるときは、そのような取り扱いをすることが公平であると考えられます。
なお、離婚から退職時期まで何年であれば退職金を財産分与の対象に含められるかという点について明確な基準はありません。
「へそくり」の扱い
婚姻中に貯められた「へそくり」も、財産分与の対象になります。
もっとも、へそくりというからには、なかなか相手には見つからないところに隠されていることでしょう。実際に見付かるかどうかは分かりません。
もし、離婚協議の際にへそくりが見つかったときは、財産分与の対象財産となります。
また、離婚時に財産分与が決まってしまっても、離婚してから2年以内に見つかったときは、その財産に対して分与の話し合いを行なうことになります。
離婚から2年を過ぎてしまってから一方の隠していた財産が見つかった場合は、財産権の侵害があったものとして、財産を隠していた相手に請求することもできます。
実家の財産は?
離婚を考えています。わたしたち夫婦には、めぼしい財産は何もありません。ただし、相手の親は資産家です。相手もいずれは親から資産を受け継ぐことになると思うのですが、離婚するときは相手の親の財産を少しでも自分はもらうことができるのでしょうか?
離婚するときの財産清算は、夫婦で作りあげた財産が対象となります。そのため、両親の財産は、あなたの離婚にまったく関係がありません。もし、相手が婚姻中に親から贈与などで財産を取得していても、その財産は財産分与の対象にはなりません。
配偶者の両親が財産家である場合、上記のような質問がよくあります。
何となく近い存在にある相手の両親の財産は将来は配偶者の財産となり、ご自分もその恩恵を受けられると期待することは、ごく自然のことかも知れません。
しかし、相談者の方が気になる相手の親の財産は、夫婦の財産とは関係ありません。
仮に、相手が贈与又は相続で親から財産を婚姻中に取得していたとしても、その財産は財産分与の対象にはなりません。
こうした夫婦の財産と関係ない夫婦それぞれの固有の財産を、特有財産と言います。
生命保険の整理
生命保険は、死亡保障が主な目的として利用されています。生命保険の死亡保障は、被保険者が死亡したときに死亡保険金が保険金受取人へ支払われます。
婚姻している夫婦であると、一般には配偶者を死亡保険金受取人に指定して加入しています。
万一の時には死亡保険金によって遺族の生活資金がまかなわれるという大切な機能が生命保険にはあります。
日本の世帯加入率は94パーセントを超え、ほとんどの家庭で生命保険に加入しています。
このような生命保険も、離婚のときには財産分与の対象になります。婚姻期間中に支払われた保険料が夫婦の共有財産としてみなされるからです。
生命保険の多くは、解約したときに解約返戻金が支払われますので、この額を財産分与の対象とすることが考えられます。
生命保険を解約する手続きは簡単ですが、解約する時には注意が必要です。
保障型の生命保険は、基本的に健康体でないと加入できません。すでに病気にかかっている場合には、一度生命保険を解約してしまうと再加入できない恐れがあります。
そのため、そのような場合、生命保険を解約しないで保険加入者が財産分与でその生命保険を取得することを考えます。
また、養育費の支払い義務者の保険をすべて解約してしまうと、義務者が死亡したときに養育費が支払われなくなります。
子どもには離婚後にも親からの相続権がありますので、相続財産がある場合は相続財産を生活資金に充てることができます。
ただし、相続の手続きには時間もかかり、預貯金などの金融資産がないと、一時的に生活費に窮することにもなりかねません。
このような事態に備えて、養育費の支払い義務者は、子どものためにある程度の死亡保障を加入しておくことが大切になります。
離婚する際には、生命保険を財産分与の対象と見るだけでなく、養育費の義務者の保障としても捉えて対応方法を考えることが求められます。
このほか、住宅の財産分与に関して住宅ローンの支払いを一方が引き受けることがあります。
金融機関との契約上の債務者と異なる場合は、団信に加入していません。このようなときは、住宅ローンの引き受け者が残債額に見合う生命保険に加入しておくことも必要になります。
財産分与請求権の相続
財産分与に関する話し合いを離婚の成立後に行なうこともあります。
事情があって離婚成立を急ぐ場合、暴力、無視などの理由によって協議が難しい場合などは、離婚の成立後に家庭裁判所の調停または審判で財産分与について定めることもあります。
財産分与の請求は、離婚の成立から2年以内に行なうことができるため、離婚の成立後に財産分与を定めることも現実に考えられます。
なお、財産分与の協議、調停の最中に、相手方が死亡してしまうこともあり得ます。
人間である以上は不測の事態が起こる可能性は無くなりません。このようなとき、財産分与はできなくなってしまうのでしょうか?
財産分与については相続を認めるとの考え方が一般的ですので、上記のような事態になってしまっても、相手の相続人に対して財産分与の請求をできると考えられます。
離婚の成立によって相続権は失っていますが、財産分与が未了のままであるので、相続人に対して協議を求めます。
なお、離婚の成立後に相手に対して財産分与請求をしていなかった場合は、財産分与の権利を相続人に対して請求できないとの考え方もありますので、注意が必要です。
離婚の成立後には財産の減少、喪失なども起こりますので、できるだけ早めに財産分与請求をしていく方が安全であると考えられます。
借金について
婚姻期間において、衣食住にかかる生活費用や医療費などを借り入れたり、未払いとなっている債務は、財産分与のなかで清算します。
不動産、預貯金などのプラスとなる財産分与の対象財産から、借り入れてた離婚時の債務額を差し引いた残りの評価額が財産分与の対象となります。
ただし、プラス財産における考え方と同様に、婚姻生活に関係なく一方側がつくった借金は、財産分与における清算対象とはなりません。
そうした性質の借金は、借り入れた本人が個別に返済する義務を負うことになります。
債務の清算があるときは、離婚協議において確認しておき、契約書に整理しておくことが、離婚後のトラブル回避のために効果的です。
わたしたち夫婦には子どもがいません。また、財産分与をする夫婦の共有財産もありません。ただ、仲が悪くなるなるまでには、一緒に旅行へ行ったり、暮らしぶりも贅沢になっていました。そのため、ローン会社から夫名義で借り入たお金が150万円位あります。この借金は、離婚のときどのようになるのでしょうか?
夫婦で使ったお金の借金は、二人に返済する義務があります。離婚のときに負担の割合を決め、借金について清算する確認書(離婚協議書)を作成しておくことをお勧めします。公正証書にすることも検討します。
夫婦での共同生活は、互いに助け合っていかなければなりません。結婚生活に必要となる費用は、夫婦がそれぞれの収入などに応じて負担します。
もし、生活費が不足したりすれば、借金することもあります。
借金の目的が、夫婦のどちらか一方による個人的な遊興費などであれば、借金した本人にすべて返済する義務があります。
でも、夫婦生活を維持するためにした借金、夫婦で使った借金であれば、夫婦が共同して返済する義務があります。
夫婦でいるうちは共同して借金を返済していけば良いのですが、離婚した後には生計も別々になります。
そのため、離婚するときには、借金の返済について清算しておきます。
借金の負担する割合を半分ずつにすることが分かりやすいですが、双方の返済能力なども踏まえて傾斜して配分することも考えられます。
借金の返済は、法律上では借り入れた名義人に義務があります。
そのため、名義人でない側は、名義人に対して借金の負担分を返済します。一括返済の難しいときは、離婚後に分割払いで返済することを約束します。
借金の清算だけを合意書に定めることもできますが、離婚時におけるそのほかの取り決めも合わせて確認をしておきます。
婚姻の解消と、借金の清算、確認事項などを定めて離婚協議書に作成します。
返済する分割金の額が大きいときは、公正証書として契約することも検討します。
夫婦間で借金を清算することは、若い夫婦に限らず、住宅ローンの返済などに関して、多くの夫婦で離婚時に整理することがあります。
借金の返済に関しては、離婚時にしっかりと清算又は整理しておくことが大切です。
請求期限などに注意
離婚するときは夫婦で財産分与についても決めておくことが必要になりますが、離婚時における夫婦の事情によっては、離婚の成立後に財産分与を話し合うこともあります。
二人の間で決まらないときは、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てます。
離婚の成立から2年以内でなければ、家庭裁判所に請求できなくなることに注意が必要です。
また、離婚後の財産分与では、対象財産が曖昧になったり、散逸してしまう恐れもあるため、期限に注意しながら、できるだけ早目に清算しておくべきです。
なお、財産分与は夫婦の共同財産を清算することが主な目的になりますので、離婚原因の有無とは直接には関係しません。
一方側に離婚原因があるときも、共同財産の清算との目的による財産分与は行われます。
離婚原因のある側が財産分与を請求することはおかしいとの気持ちがあるかもしれませんが、法律上では離婚原因の有無と財産分与は基本的には分けて考えます。
給付金の支払い方法
離婚の成立したときに財産分与の給付額を一括して支払うことが原則になります。
ただし、財産分与の対象財産が不動産中心であるときなどは、財産分与の給付額にあたる預貯金がないこともあります。
そうしたときは、離婚後に不動産を売却して清算をしたり、不動産を取得する側が代償金を分割して支払うことになります。
また、扶養的財産分与は離婚後の定期金による支払いが一般的であり、退職金にかかる給付は数年先の定年時になることもあります。
このように、離婚時に清算の完了しない財産分与給付については、離婚時に公正証書を作成するなどして、双方で確認をしておくことが必要になります。
賃借している不動産
賃借している土地に住宅を建て夫婦で住んでいたところ、離婚によってその住宅が妻に対して財産分与として譲渡されたとき、その土地の賃借権の妻への譲渡に関しては地主の承諾はいらないとした裁判例があります。
一方が所有する土地・建物のうち建物だけを財産分与したときは、土地は使用貸借(無償で貸す)や賃貸借(賃料を設定して契約する)を設定することが考えられます。
扶養的財産分与
夫婦の共同財産がなく、慰謝料の支払いもなく、固有の財産もないときに離婚をすることで、一方側がただちに生活に困窮することが予想されることがあります。
専業主婦として家事、育児に専念していた妻側にそうした問題が起きることがあります。
長く専業主婦を続けていたり、乳幼児を抱えている妻が離婚をしても、ただちに仕事によって生活できるだけの収入を得ることは容易なことではありません。
このようなとき、夫婦に清算する共同財産がないときでも、そうした妻の離婚後における生活支援を目的として、扶養的財産分与が定められることがあります。
夫婦には法律上で協力扶助義務がありますので、婚姻中は夫婦は互いに同等水準の生活をする権利義務がありますが、離婚によってこの権利義務は消滅します。
そのため、離婚した後に、同等水準までならなくとも、妻がそれなりに生活できるまでの定期金を一定期間にわたり支払うこともあります。
なお、扶養的財産分与は一般の方にはほとんど知られていない知識であり、また、扶養的財産分与を行なうには一方に十分な資力のあることが前提になります。
そうしたことから、それほど多くの離婚で行なわれている訳ではありません。
当事務所で扱う離婚契約でも扶養的財産分与が定められることがありますが、離婚するものの夫婦の関係がそれほど悪くなく、一方に十分な収入のあることが傾向として見られます。
扶養的財産分与をしなければ妻側が厳しい生活を強いられることが見えていても、若い夫婦であると、扶養的財産分与が定められるケースはほとんど見られません。
おそらく妻側は離婚して生活に困ったときは、実家からの支援を受けたり、公的扶助の制度を利用することになるのでしょう。
なお、熟年離婚においては、扶養的財産分与が必要になることも多いと思われます。
離婚するときには、夫婦で財産を分ける財産分与があると聞きました。でも、私たち夫婦には分けるべき財産もありません。また、結婚前から貯めていた貯金などもありません。夫には仕事がありますが、私は今は仕事をしていないので、離婚してからの生活が厳しくなるのですが、どうしたらいいでしょうか?
経済的に余裕のある生活を送っている夫婦は、それ程多くありません。そのため、離婚時に財産分与の対象財産がない夫婦も結構見られます。男性は、離婚しても仕事を続けますので、生活するに心配ありません。しかし、女性は、結婚・出産時に仕事を辞めてしまっていることが多くあり、離婚からしばらくは生活が厳しくなります。そうしたとき、離婚条件の一つとして、扶養的財産分与として一定期間、毎月定期金を受け取ることを約束することがあります。
離婚することで経済的に厳しい状況になるのは、どうしても妻側になります。
妻側は、結婚するとき、出産するときに仕事を辞めてしまうことが多いことから、離婚してからも直ぐには経済的に自立して生活していくことが難しいことがあります。
離婚の際における財産分与によって、預貯金などからある程度の給付が行なわれると、離婚からしばらくの間の生活資金となります。
しかし、夫婦の共同財産となる預貯金を持たない夫婦は、珍しいことではありません。
若い夫婦で早くに住宅を購入していると、預貯金等の資産を持っていないだけでなく、離婚する時点では負債額の方が圧倒的に多いこともあります。
不貞行為などの明確な離婚原因がないときには慰謝料が支払われないことが多く、結婚する前からの預貯金(特有財産)もそれ程ないものです。
財産分与の対象財産がなかったり、慰謝料の支払いもなければ、離婚した後は資金ゼロから新しい生活をスタートしなければなりません。
夫側は仕事によって十分な収入を継続して得られますが、妻側はそうなりません。
こうした状況であるとき、扶養的財産分与として離婚からしばらくの間、夫側から妻側へ生活資金を毎月支払う約束をすることがあります。
この扶養的財産分与の支払期間は、それぞれの事情、考え方によって決められますが、一般には1年から3年程度とされています。
妻側が離婚してから職業訓練を受けることもあれば、契約社員などから就労することもあります。そうした訓練などに必要な期間だけ生活資金を支援します。
こうした扶養的財産分与を約束できることで、互いが離婚に向かうことができます。
離婚の合意をするためには、気持ちだけでは足りず、現実的な経済環境を整えることも必要になります。
定期金の支払いが何年間か続きますので、支払総額も小さなものではなくなります。
扶養的財産分与は親族間の扶養義務とは異なり、夫婦の婚姻を解消した後における給付になりますので、扶養という名目であっても実質的には契約になります。
そのため、夫婦で取り決めた扶養的財産分与の支払い約束が着実に履行されるように、離婚協議書(公正証書)に作成しておくことが大切になります。
財産分与等の離婚契約書サポート
夫婦での財産分与の取り決めは、その対象となる財産額の多寡に関わらず、離婚した後にトラブルの起きないように離婚協議書(公正証書)に作成しておくことをお勧めします。
夫婦の共同財産がないときにも一方側に借金があったり、婚姻中に借り入れた住宅ローンの返済がまだ続いていることもあります。
安心して離婚後の新しい生活に向かうことのできるように、婚姻中のことは離婚協議書にすべて整理をしておくことが安心です。
重要な離婚協議書になりますので、ネット上で掲載されているひな型を改変して作成するのではなく、専門家に相談、確認して作成しておくことが将来の安心につながると考えます。
相談料、期間中の案文修正も、すべて含まれるパッケージ料金となっております。
離婚協議書(公正証書)の作成サポート
相談料、期間中の案文修正も、すべて含まれるパッケージ料金となっております。
ご利用料金(税込)
離婚相談から離婚協議書の作成まで (1か月間サポート保証) | 3万4000円(税込み) |
|---|
離婚相談・公正証書の作成支援 (3か月間サポート保証) | 5万7000円(税込み) |
|---|
【離婚相談から離婚協議書作成までのフルサポート(1か月間保証)】
- 協議離婚の諸条件(財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
- 離婚協議書の原案作成、修正
- 離婚協議書の完成
- 離婚協議書の契約用紙への印刷、引渡し
【離婚相談から公正証書作成までのフルサポート(3か月間保証)】
- 協議離婚の諸条件(養育費、財産分与、慰謝料など)のご説明および相談※
- 離婚契約公正証書(案)の原案作成、修正、完成
- 公証役場への申し込み
- 代理取得できる資料の収集
- 公証役場との公正証書案の調整、連絡
※離婚相談は、サポート契約の期間中は何度でもご利用になれます。
住宅の財産分与があるとき
夫婦の共同財産に住宅のあるときは、住宅ローンが返済中であることも多くあります。
このようなときに住宅の財産分を行なう場合は、住宅の所有権を確認するほか、住宅ローンの負担、連帯債務の解消などの整理も必要になります。
そのため、離婚時には離婚協議書(公正証書)を作成する必要性が高くなります。
こうした財産分与の契約は、夫婦双方にとって重要なものとなることから、必要に応じて住宅ローンの債権者である銀行とも調整をしながら、とくに慎重にすすめなければなりません。
離婚専門の行政書士として、多数の離婚協議書、離婚契約公正証書の作成に携わってきています。
ごあいさつ・略歴など
財産分与の契約は重要です
財産分与は預貯金だけが対象になるばかりではなく、婚姻中に購入した住宅も対象になります。
夫婦のどちら側が住宅を取得するかによって、離婚後の住居にも影響があります。
離婚に伴って住宅を売却することもあり、その場合は売却時における手続き、清算などを取り決めておきます。
住宅を売却しないときは、住宅ローンの返済をどうするか夫婦で確認することが必要になります。
住宅ローン以外にも、夫婦の双方または一方に借金のあることもあり、その返済確認も行なっておきます。
こうした財産分与の整理は、離婚協議書に取りまとめておくことが大切になります。
専門家へ離婚協議書の作成を依頼されることをお考えであれば、お問い合わせください。
離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
- 離婚協議書
- 離婚条件を定める公正証書
- (別居時における)婚姻費用の分担契約
- 夫婦間の誓約書
- 不倫問題に対応する示談書
- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
離婚協議書作成サポートのお申し込み

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
事務所のご案内
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

運営元
船橋つかだ行政書士事務所
住所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
アクセス
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋駅から徒歩4分
ごあいさつ

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
ご利用者様の声175名
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)
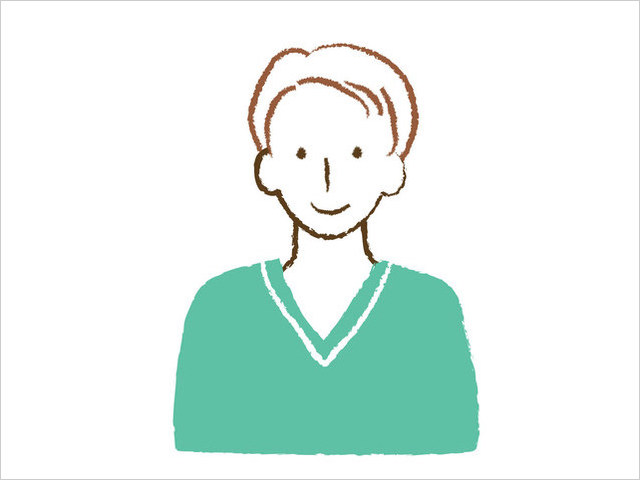
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)
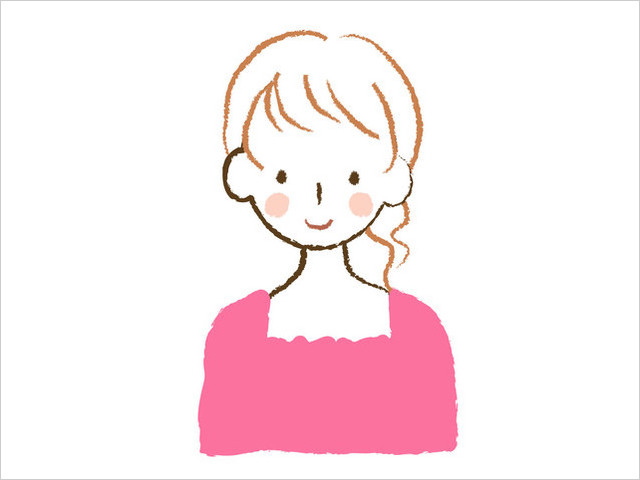
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

