離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
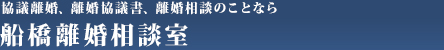
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
|---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらへ
父母の一方が親権者になります
親権者の指定
離婚するときには、夫婦の間に生まれた未成年の子どもそれぞれについて父母の一方を親権者に指定しなければなりません。
親権者を定めないと協議離婚届が受理されないため、夫婦で親権者の指定に合意できない場合は家庭裁判所に親権者を定める申し立てを行います。
離婚に伴う単独親権への変更

法律上の婚姻関係にある夫婦に生まれた未成年の子どもの親権は、父母が共同して行ないます。(これを「共同親権」といいます)
親権は、未成年である子どもの身の回りの世話、しつけ、住まいの指定などを行なう「身上監護権」と子どもの財産管理、契約代理などを行う「財産管理権」とから構成されています。
父母が婚姻している期間は、父母が共同して親権を行使しますが、離婚すると、父母のどちらか一方だけを親権者に指定することになっています。(これを「単独親権」といいます)
こうした法律上の制度から、協議離婚の届出においては必ず夫婦の未成年の子どもそれぞれについて親権者の指定をしなくてはなりません。
もし、夫婦の間での協議では親権者を決められなければ、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立て、調停で決めていくことになります。
このように、離婚するときは、離婚条件のうちでも未成年者の親権者を指定することだけは必須事項となっていることから、夫婦間に親権者の指定に争いがあると離婚できません。
夫婦の間における感情的な軋轢が大きい場合には、親権者の指定が離婚条件を取り決める際に駆け引き材料として利用されることも起こります。
子どもの親権者が決まらなければ、そのほかの子どもに関する面会交流や養育費の条件についても話し合いがすすみませんので、協議離婚を行うことが難しくなります。
夫婦の間における協議又は家庭裁判所における調停によっても親権者が決まらないときは、最終的には裁判で争うことになります。※審判による方法もあります。
家庭裁判所では、次の要素によって親権者を定めるものとされています。
- 母性の優先
- 継続性の原則
- 兄弟不分離など
子どもが乳幼児などの場合には、親権者は母親になることが多くあり、協議離婚においても、多くのケースで母親が親権者になっています。
もちろん、子どもとの関わり具合、生育環境、母親の実状を勘案して父親が親権者となるケースもありますので、はじめから母親になると決めつけてかかってしまうのもいけません。
また、原則としては親権者が子どもを監護養育することになりますが、夫婦の合意があれば、親権者と監護者(実際に子と共同生活する者)を別々に分けることもあります。
このような取り決めをすることを法律実務では「分属」といいます。
離婚してからも父母で共同して子どもを育てる形とになるため、父母の関係があまり良好でないケースでは、子どもをめぐってトラブルが離婚した後に起きることも心配されます。
そのため、家庭裁判所の実務では、原則として親権と監護権の分属を認めない方向です。
ただし、協議離婚では、親権、監護権ともに夫婦の話し合いで決めることができます。
なお、離婚の成立後に親権者の指定を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
親権者を変更することは子どもにとって大きな影響を及ぼすことになるため、父母の判断だけでは決めることができず、必ず家庭裁判所が関与する仕組みになっています。
なお、監護者については、離婚後でも父母の話し合いだけで変更することができます。
監護者の変更について父母の間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停又は審判で決めることになります。
別居中における子の監護
離婚する前に夫婦が別居しているときは、夫婦による共同親権は変わりませんが、夫婦のどちらか一方が子どもの監護者となっている状態にあります。
この別居期間に夫婦のどちら側が子どもの監護者になるかについて夫婦の間で争いになってしまうことがあります。
離婚するときの親権者の指定への影響を考えて、あらかじめ子どもの監護者になっておこうとして、夫婦での合意を経ずに一方が子どもを連れ去ってしまうことも起きます。
このような子どもの監護者に関して夫婦の間に争いが起こったときは、家庭裁判所に対し監護者の指定を受ける審判を申し立てます。
子どもに関する問題については、夫婦の問題と同じく家庭裁判所で取り扱います。
子の監護者の指定調停
実親と養親との離婚
連れ子での再婚では、自分の子どもを新しい配偶者と養子縁組させることが多く見られます。
このような再婚が解消される(離婚になる)ことになるときには、同時に養子縁組も解消されることが一般には見られます。※解消しないこともあります。
この場合、離婚の手続きに合わせて離縁の手続きを行います。
先に離縁の手続きをした後に離婚することも見られますが、どのような手順で手続きすることが良いかは、それぞれのケースに応じて検討することになります。
戸籍に関しての確認は、住所地の市区町村の戸籍係に尋ねると丁寧に教えてくれます。
親権と監護権の分離(分属)

離婚のときに未成年の子どもがある場合、父母のどちらか一方を親権者として指定しなければなりません。
この親権者を決めるとき、子どもの親権者について父母で話し合いがつかないことがあります。
父母の両者が親権者になりたいと主張すると、互いに譲り合わず、容易には決着しません。
離婚に伴い親権者の立場を失うことになる親側の気持ちとしては、子どもを喪失する意識を持ってしまうことになって辛いのでしょう。
父母のどちら側も譲らないときに、親権と監護権を父母の間で分けることがあります。これを分離又は分属と言い、実務上でも行われています。
監護権は、親権に含まれる権利の一部であり、子どもの教育、生活指導、住まいの指定などに関して子どものために行使する権利になります。
なお、子どもの財産管理については監護権に含まれていません。
協議離婚の届出において親権者の指定をすることが必須となっていますが、そこでは監護権者については何も触れられていません。
親権者と監護権者は父母の話し合いで決めることができ、話し合いでは決まらないときには、家庭裁判所の調停等で決めることになります。
原則は、親権者が子どもの監護養育に関するすべてを行なうことになります。家庭裁判所の実務でも、親権者と監護権者を分けて指定することは原則として行いません。
親権から監護権を分離させることは、子どもの育成面で良い面と良くない面があります。
良い面としては、父母が離婚してからも、子どもの育成に父母が責任を持ち関わっていけるということです。子どもからは、父母から育てられている実感が持てるでしょう。
良くない面としては、離婚した父母が子どもの育成を行うことで不都合が生じることです。
一方側だけで決められないことがあれば、父母で話し合うことになりますが、離婚した父母の話し合いでは意見が対立して円満にまとまらないことが予想されます。
ただし、子どもの福祉の観点から必要であると認められるときには、家庭裁判所においても、監護権者を親権者ではない側に定めることもあります。
養子縁組のとき
親権と監護権の分離(分属)については、共同親権が継続する面もあります。
法律上での基本的な仕組みとしては離婚した後は単独親権になることを想定していますので、家庭裁判所では分離(分属)は例外的な手続となります。
たとえば、子どもが15歳未満であるとき、氏の変更、養子縁組の承諾に関しては、親権者は子どもの代理権を有することになります。
そのため、子どもの監護権だけを持った親が再婚したとき、再婚した相手と子どもの間に養子縁組をしたくとも、親権者の承諾を得られなければ養子縁組をすることができません。
このようなときに、養子縁組の手続きが円滑にすすめられるか分かりません。
親権者は子どもの法定代理人となりますので、親権を有しないで他方の親が監護者となると、子どもの監護における実務などでは不自由な場面が出てくることになります。
離婚後に親権者を変更する

協議離婚の届出には親権者の指定が必要になるため、夫婦の協議によって離婚した後の親権者をどちらか一方に指定しなければなりません。(単独親権)
では、離婚が成立した後に親権者を変更したいときはどうなるのでしょうか?
離婚した後における親権者の変更は父母だけで行なうことが認められていません。家庭裁判所の許可が必要になります。
親権者を変更したい側は、家庭裁判所に対して親権者を変更したい旨の調停又は審判を申し立てなければなりません。子どもの父母以外でも子どもの親族であれば申し立ては可能です。
家庭裁判所は、親権者の子どもに対する監護能力、経済状況、健康状態などのほか、子どもの年齢、兄弟姉妹の状況、環境への適応力などを踏まえ、親権者の変更を判断します。
家庭裁判所では、子どもが15歳以上であるときは子ども本人の考えも聞きながら、子どもの利益を優先して判断されます。
親権者が父母のどちら側になるかは、未成年である子どもに大きく影響する重要なことになるため、親権者変更の判断は慎重になされます。
とくに途中から親権者を変更することになるため、変更をした方が子どもの利益になるという相当の事情が必要になります。
単独の親権者が死亡したときは、法定代理人となる未成年後見人を選任するか、又は親権者の変更をするかを、関係者からの申し立てに応じて家庭裁判所が判断することになります。
親権者の変更はむやみに行なうことができないため、離婚協議するときには夫婦で慎重に親権者の指定について話し合っておくことになります。
親権者変更の約束
離婚するときは、子どもの親権者の指定について夫婦で話し合われます。
双方とも親権者になりたいとき、親権者と監護者を分けることが行われることもあります。
上記にある記載のとおり、これはあまり一般にとられる方法でありませんが、夫婦による取り決めとしては有効になります。現実にそうした定めをして離婚する夫婦もあります。
なお、夫婦の話し合いにおいて、離婚の成立後に親権者を変更する条件を定めておきたいという方があります。
離婚時に指定した親権者が子どもの監護を十分に行なわないときは親権者の変更を認めるというようなことを契約しておきたいというものです。
しかし、親権者の指定に期限又は条件を付けることは、法律的には認められないことです。
離婚後に親権者側に何らかの問題が起こったときは、家庭裁判所へ変更の申し立てをします。
単独親権者が死亡したとき

婚姻期間にあると父母による共同親権になりますが、離婚した後には父母のどちらか一方だけが親権者になります。
そのために、離婚後に親権者が亡くなってしまうと、一時的に親権者が不在となる状態になります。
民法では親権者がいなくなったときは、未成年者について後見が開始することになっています。
「後見(こうけん)」とは法定代理のことであり、未成年後見人は、親権者が行なうべき未成年者の財産管理と監護教育を代わりに行ないます。
未成年後見人は、未成年者本人やその親族などの関係者から、家庭裁判所に選任の申し立てが行われます。
家庭裁判所では、未成年に関する様々な情報、子ども本人の意見も聞きながら、未成年後見人の選任を行ないます。
なお、万一のときに家庭裁判所への選任依頼をしなくとも済むように、最後の親権者となる者が遺言により未成年後見人を指定しておくこともできます。
夫婦での共同親権を行使できるときは、万一における親権者のことを心配しないと思います。
しかし、離婚によって単独親権になったときは、自分(親権者)に万一のときに備えて、遺言で頼れる人(親など)を未成年後見人として指定しておくと安心であると思います。
遺言の方法は、未成年後見人の指定だけであれば、本人が書く自筆証書遺言でも足ります。
ただし、自筆証書遺言であると、相続の開始した後に家庭裁判所への検認手続きが必要となりますので、手続に時間がかかります。そのため、公正証書遺言が便利であると言えます。
もし、遺言による未成年後見人の指定がないとき(未成年後見人が指定された後も)は、離婚により親権を失くした親側から、家庭裁判所に対して親権者の変更を申し立てられることもあります。
この場合における親権者の変更は、その変更をすることが子どもの福祉に適うものであるか、との観点から家庭裁判所で判断されることになります。
親権者は、親以外の者がなることはできません。ただし、新たに養子縁組が結ばれたときは、その養親が子どもの親権者となります。
「未成年後見人の指定」と「親権者の変更」
父母一方の死亡や離婚により単独親権の状態となっているとき、万一の親権者の死亡時に備えて、遺言により未成年後見人を指定しておくことができます。
しかし、離婚による単独親権では、ほとんどで非親権者である親が生存しています。
このようなとき、未成年後見人が子どもの法定代理人となっても、非親権者の親から親権者の指定に関する申し立てが家庭裁判所に対して起きることも考えられます。
このようなとき、家庭裁判所では、未成年後見人の選任か、親権者の指定か、どちらが未成年者のために良いかを判断して選択することになります。
再婚相手と子の養子縁組

離婚した後に子どもの単独親権者となった親が再婚したときは、再婚相手と自分の子どもを養子縁組させることがよく行われます。
そのときに子どもが15歳未満であると、親権者の代諾により養子縁組が行われます。
この養子縁組によって、その子どもは単独親権から共同親権に移行することになります。
このときに非親権者から親権変更の請求をしても、実際上は認められていないようです。
子どもの福祉の観点からは、新しい両親による共同親権の元で監護養育を受ける方が、特別の事情がない限り、望ましいことであると考えられるのでしょう。
子どもと同居していない実親の気持ちとしては複雑なところもあるでしょうが、子どもの福祉の観点から考えて、そうした判断を受け容れることになると思います。
なお、養子縁組をした後における面会交流の実施については、養子縁組によって子どもの環境が変わりますので、注意が必要になります。
子どもにとっては養子縁組によって新しい親ができたのですから、何らかの気持ちの整理をつける期間が必要になります。
離婚する時に定めた面会交流の条件を変えずに面会を継続することが、子どもの精神面に対して良いことになるかを、実父母の間で考えて話し合うことが必要でしょう。
もし、子どもに良くない影響が出る心配があれば、少しのあいだ子どもの様子を見ながら、面会交流ルールの見直しを検討しなければなりません。
面会の実施は、養親となった側にも重要なことになります。当事者となる者が子どもの福祉を優先しながら、納得できる解決方法を見付けることになります。
また、子どもが成長して精神的に成熟してくることによって、実親と面会交流を持つことも、いずれは問題とならないことになると思われます。

離婚協議書の作成支援
夫婦で子どもの親権者の指定をしておかないと、協議離婚の届出を役所は受理しません。
そのため、離婚することには夫婦で合意ができても、親権者を決められないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。
船橋離婚相談室は行政書士事務所が運営していますので、協議離婚における各契約書(離婚協議書など)を主な業務としています。
したがいまして、家庭裁判所の調停又は裁判に関する手続のご案内又は相談には対応することができませんことを、ご理解ねがいます。
もし、ご夫婦で親権者を決めることができずお困りである場合は、離婚問題に詳しい弁護士にご相談ください。
船橋離婚相談室では、これから協議離婚をされる方、すでに協議離婚をしている方の離婚条件を定める離婚協議書などを作成するサポートをメイン業務としています。
夫婦の間で親権者の指定が決まっていて、養育費や財産分与などについての取り決めを、離婚協議書又は公正証書に作成したいとお考えになられている方を対象にして、条件の定め方などについてご相談いただきながら、離婚協議書等を作成いたします。
ご利用を希望される方は、「フォーム」または「お電話」でお問い合わせください。
離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
- 離婚協議書
- 離婚条件を定める公正証書
- (別居時における)婚姻費用の分担契約
- 夫婦間の誓約書
- 不倫問題に対応する示談書
- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
離婚協議書作成サポートのお申し込み

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
事務所のご案内
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

運営元
船橋つかだ行政書士事務所
住所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
アクセス
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋駅から徒歩4分
ごあいさつ

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
ご利用者様の声175名
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)
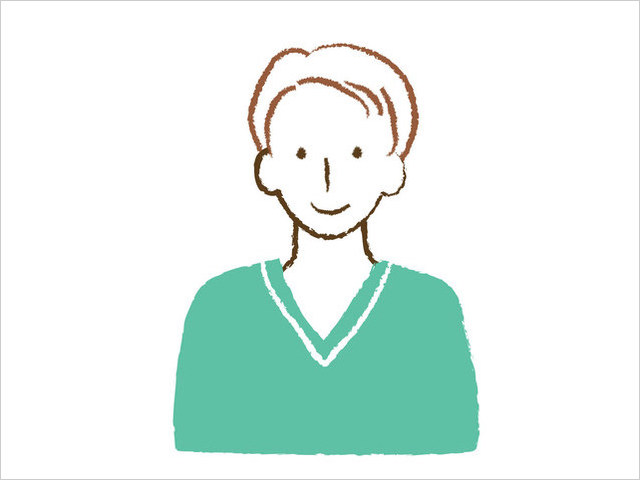
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)
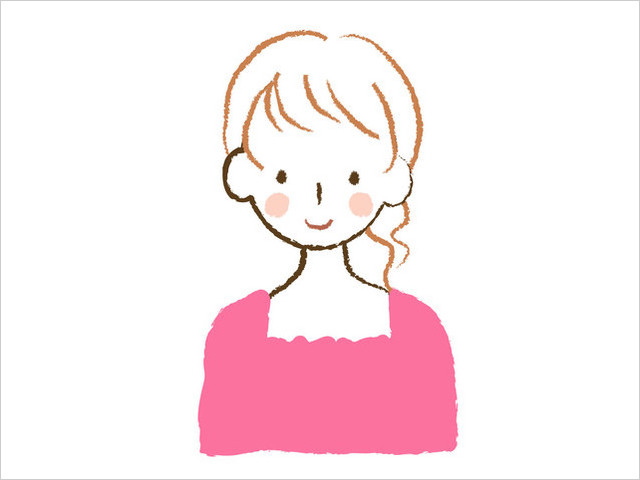
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
