船橋ほか全国から離婚協議書・公正証書の作成(離婚相談)に対応します。土日営業・平日は夜9時まで
船橋駅4分の離婚協議書等専門の行政書士事務所<全国対応>
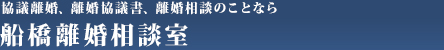
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~20時(土日9時~17時) |
|---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらから
生命保険の死亡保障機能を活かす
離婚契約に生命保険を利用する
貯蓄性のある生命保険契約は、解約返戻金相当額が財産分与の対象になります。また、死亡保障機能のある生命保険契約は、離婚契約の債務者の死亡に備えて利用されることもあります。たとえば、養育費の支払期間中は生命保険契約の死亡保険金受取人を債権者若しくは子どもに指定しておくことで、養育費の債務者が死亡したときに死亡保険金を養育費に充当します。
死亡保障機能を利用する

解約すると返戻金を受け取れる貯蓄性のある生命保険契約は、財産分与の対象となります。
こうした財産分与として生命保険を評価するほかに、死亡保障機能を離婚契約に利用することもあります。
離婚にかかる金銭給付のあるとき、債務者が金銭の支払いを完了する前に死亡してしまうと、その相続人が債務を引き受けます。
しかし、養育費の債務は、財産分与や慰謝料とは異なり、相続の対象になりません。
そのため、債務者(養育費の支払義務者)が支払い期間中に死亡したときに備えて、生命保険契約を利用することがあります。
支払い義務者が生命保険契約の契約者及び被保険者として加入する生命保険契約の死亡保険金受取人を債権者(養育費の受取人)又は子どもに指定しておくことで、養育費の支払い期間中に債務者が死亡したときに死亡保険金を養育費に充当することにします。
ただし、養育費の債務者が生命保険契約に加入する法律上の義務はありません。
あくまでも父母間の話し合いで、生命保険契約を利用する約束を交わしたり、債務者自らの判断でそうした対策を講じておきます。
このほか、財産分与のなかで、離婚した後における住宅ローン負担者を、夫婦の間においてローン契約名義人から他方側に変更することがあります。
財産分与によって住宅を所有する側が住宅ローンを負担する整理方法は一般的なものです。
このときに、新たに住宅ローンの実質的な負担者となる側は、団体信用生命保険に加入していませんので、返済中に死亡したときは他方側に債務を負担させてしまうことになります。
そうならないために、新たなローン負担者が契約者及び被保険者として加入する生命保険契約の死亡保険金受取人を他方側に指定しておくこともあります。
これらの生命保険の活用は、夫婦の間による契約で離婚協議書に定めます。
ただし、生命保険契約は保険会社と契約者の間における契約であるため、契約者は保険契約を変更したり解約することが可能であることに注意を払うことが必要になります。
そのため、住宅ローン契約で利用される団体信用生命保険のように、金銭の支払いを担保するシステムとして設定することまではできません。
税金の取扱い
生命保険契約の契約者は、保険契約の変更又は解約を行なう権利を持っています。
離婚契約に生命保険契約の死亡保障機能を利用するときは、保険契約者の側が夫婦の間で交わした約束をきちんと履行することが前提になります。
生命保険を活用することで利益を受ける側が生命保険の契約者になる対応も考えられますが、契約者と被保険者が異なるときは、死亡保険金の受取りで税金上のデメリットを受けます。
生命保険契約では、契約者、被保険者、保険金受取人をどのように設定するかによって死亡保険金を受取るときの課税が変わります。
そうしたことから、離婚契約で生命保険契約の利用を考えるときは、税金面における確認をしておくことが非常に大切になります。
また、保険契約の種類によっては、契約変更に対応できる範囲について制約がありますので、加入している生命保険会社に事前に確認してから契約対応を検討します。
| 契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
| 夫 | 夫 | 相続人など | 相続税 |
| 妻 | 夫 | 妻 | 所得税 |
| 妻 | 夫 | 子 | 贈与税 |
- 相続税
支払われた保険金は相続税の対象になります。
ただし、保険金受取人が相続人のときは、次の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人の数
- 所得税
一時所得=(保険金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)
課税対象は、一時所得の2分の1です。
- 贈与税
贈与税の課税対象となる金額=保険金-基礎控除(110万円)
上記の仕組みは基本ですが、詳しくは、加入する生命保険会社にご確認ください。
なお、生命保険契約に関するご相談の際には、保険証券など、加入済の生命保険契約の分かる資料をお手元に置いておくとスムーズに話が進みます。
離婚契約に生命保険を利用する
離婚相談の船橋離婚相談室
ご不安を解消する離婚・不倫サポートのお問合せ
協議離婚するために離婚協議書又は公正証書を作成したい方、不倫問題への対応が必要な方の各サポートのご利用に関する相談に対応いたします。
【お願い・ご注意】
- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応には時間がかかります。そのため、ご利用者の方には各サポートで対応させていただいております。
- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、具体事例についてのアドバイスには無料相談で対応しておりません。

「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書又は公正証書、示談書などを急いで作成する必要があるときは、速やかに対応させていただきますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応いたします。
〔サポート対象となる書面〕
- 離婚協議書
- 離婚の公正証書
- 婚姻費用の分担
- 夫婦間の誓約書
- 不倫問題の示談書
- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。
*離婚情報の説明、アドバイスには対応していません。
047-407-0991
土・日も営業、平日は夜9時(電話受付は夜8時)まで営業。
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所
離婚契約書作成サポートの「離婚相談」を受付中

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書等のサポートのご利用に関することに限らせていただいております。
047-407-0991
平日9~20時(土日17時迄)
ご連絡先はこちら
離婚相談の付いた離婚協議書・離婚公正証書の作成なら
『船橋離婚相談室』

運営元
船橋つかだ行政書士事務所
住所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号
アクセス
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~20時(土日:17時)
お申込み等のご相談はこちら
船橋駅から徒歩4分
ごあいさつ

代表 塚田章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるご依頼者の方の不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかり丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
なぜ「公正証書」に?
離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
なぜ、公正証書だと
心配が解消するの?普通の離婚協議書とどう違うの?
なぜ協議離婚では公正証書が利用されるのですか?
ご利用者様の声151名
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)
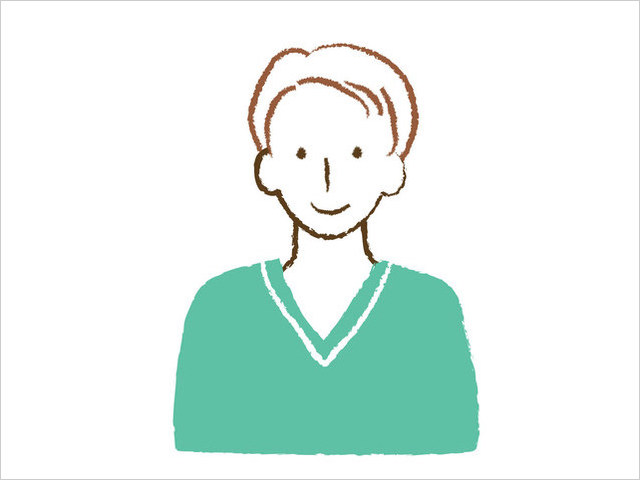
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)
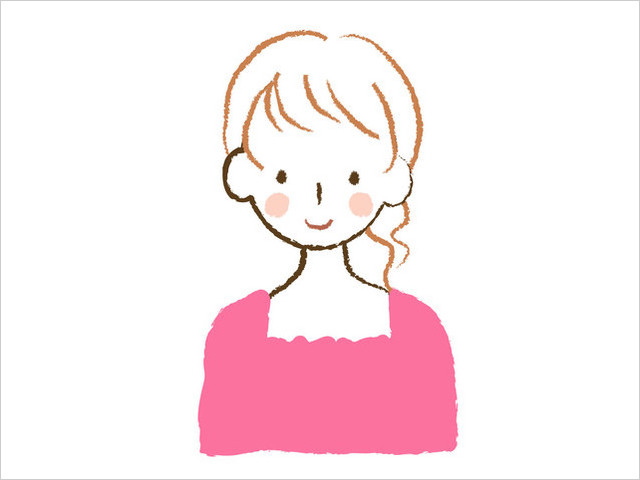
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
