離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
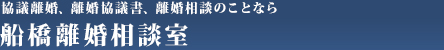
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
|---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらへ
婚姻期間の生活費は夫婦双方で分担します
婚姻費用
婚姻費用(こんいんひよう)は、婚姻した男女が生活するうえで必要となる住居、食事、子どもの教育費などの費用であり、夫婦で収入、資産などに応じて分担します。
夫婦が円満に同居生活をしているうちは婚姻費用が問題となりませんが、夫婦に何らかの問題が起きて別居する事態になった場合、婚姻費用の分担額を取り決めることが必要になります。
夫婦で分担する婚姻費用
夫婦で共同生活をおくるためには、食費、住居費、水道光熱費、医療費、生活雑費がかかり、子どもがある夫婦であれば、子どもの生活費、教育費、習い事の費用なども必要になります。
このような夫婦の婚姻生活に必要となる費用を「婚姻費用(こんいんひよう)」といいます。
夫婦が円満に生活している状態であれば、例外的な場合を除き、婚姻費用の分担について夫婦の間で問題にあがることになりません。
しかし、夫婦の関係が円満さを欠くようになったり、別居する状態に至るとき、夫婦の間で婚姻費用をどのように分担するかという問題が起きてきます。
婚姻費用(民法760条)
【民法760条(婚姻費用の分担)】
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
夫の浮気が原因となって夫婦の関係が悪くなり、もう離婚もやむを得ないという状態になっています。夫は、私と子どもを置いて、家から出ていきました。
しかし、夫は生活費を入れてきません。私は、子どもが幼いためにパート収入しかありません。でも、この収入だけでは生活できません。別居したら、もう生活費を受け取ることはできないのでしょうか?
法律上の夫婦である以上は、必要になる生活費を配偶者から受け取れる権利があります。そのため、配偶者に婚姻費用を請求できます。
もし、配偶者が支払いに応じなければ、家庭裁判所に婚姻費用請求の調停を申し立てます。
夫婦である二人がそれぞれの収入、資産に応じて婚姻生活のために必要となる生活費を分担すべきことは、法律に定められています。
この夫婦の間における婚姻費用の分担義務は、夫婦が別居することになっても変わらないものです。
したがって、離婚の届出が受理されて離婚が成立するまで、お互いに分担義務を守らなければなりません。
しかし、夫婦が別居する状況になってくると、お互いの関係は疎遠となり、それまでのように生活費が払われないことが現実に起きてきます。
共同生活する間は生計が一つであったものが、別居することで二つに分かれるため、住居費、水道光熱費など、生活上の固定費が二重でかかり、別居中の経済状況は厳しくなります。
そのため、それまでの水準で生活費を負担することが厳しくなります。
また、不貞行為を原因に別居した場合では、さらに状況が複雑になることもあります。
いずれ離婚することが避けられない状況になっていても、夫婦の間にある扶養義務は原則として完全に消滅することにはなりません。
もし、婚姻費用を分担する義務を守らず、経済的に困窮している相手に対して生活費をまったく入れないことは、あとで問題にもなります。
夫婦の間で婚姻費用が問題となったならば、話し合って婚姻費用の分担を決めることを目指します。
もし、夫婦で解決に向けて話し合うことができない状況であれば、一方は家庭裁判所に婚姻費用請求の調停または審判を申し立てることもできます。
上記のご相談者については、現状のまま放置すると生活に窮することは明らかであり、直ちに家庭裁判所に婚姻費用請求の調停を申し立てることになります。
なお、別居により婚姻費用を請求するとき、自分が住む住宅にかかる住宅ローンが支払われている場合、この負担分を婚姻費用の算定で考慮することになります。
また、離婚するときに約束通りに婚姻費用が支払われていなかった場合は、婚姻費用の未払い額を離婚時に清算することもあります。
もし、離婚時に清算できる資金が用意できなければ、離婚後に分割して払う契約を離婚協議書で定めます。
婚姻費用が問題となるとき(不仲、別居など)
同居生活をする夫婦では、主に妻が家計の管理を行っていることが見られます。
家庭の経済生活が安定している状態にあれば、何かの事情によって一時的に大きな出費が発生しない限り、婚姻費用を意識することもありません。
勤務先の経営状況が悪化して給与が下がるなどして家庭の経済収入が大きく減少するときは、家計を見直して生活を維持していかなければなりません。
この場合でも、夫婦の関係がある程度まで円満であれば、夫婦の話し合いで家計を調整していくことができます。
婚姻費用について問題となるのは、夫婦の関係が円満さを欠くようになったときです。
夫婦の関係が悪くなると、夫が家計に生活資金を入れなくなったり、夫から渡される生活資金が減額されることがあります。
こうなると、同居していても経済面で生活が厳しい状況になる場合もあり、婚姻費用の分担について夫婦で話し合うことが必要になります。
また、不仲が理由で夫婦の一方が家から出ていってしまうことがあり、従来どおりに生活費が渡されないことも起きてきます。
別居となれば夫婦の生活が別々となって家計が二つに分かれることになり、その後の婚姻費用の分担方法を決める必要が出てきます。
以上のように、夫婦の関係が悪化すると、同居、別居にかかわらず、婚姻費用の分担を取り決めることが必要になることがあります。
別居中の婚姻費用

夫婦には同居して共同生活する義務があります。
ただし、事情により別居することも認められており、法律上の婚姻関係にある夫婦である期間は、婚姻費用の分担義務は原則として消滅しません。
そのため、たとえ夫婦の不仲などを理由に別居することになっても、それぞれが生活できるよう経済的にお互いで助け合うことが求められます。
ただし、これには例外もあり、自ら夫婦の関係を壊すような不貞行為などの別居となる原因をつくった側から他方側に対し婚姻費用を請求する場合、婚姻費用の請求が信義則上から認められないこともあります。
また、そうした事情で婚姻費用が認められても、請求する側が未成熟子を監護している場合の子の生活費に限られるなど、婚姻費用の分担に制約を受けることになります。
どのように婚姻費用を決めるか?

まずは夫婦で話し合って婚姻費用の分担額、支払い方法などを取り決めることが普通です。
弁護士による代理交渉は費用がかかり、家庭裁判所の利用は期間を要するからです。
参考になる資料として、家庭裁判所で使用されている「養育費婚姻費用算定表」があります。
この算定表は法律で定めているものではありません。
あくまでも、婚姻費用を検討するうえでの目安としてご利用になられるのが宜しいと考えます。
各家庭における家計の状況は様々であり、公表されている算定表は参考モデルであり、すべての家庭に当てはまるとは言えません。
もし、夫婦の話し合いで婚姻費用の分担等が決まらない場合、家庭裁判所における調停、審判によって定めることになります。
いつから請求できる?
婚姻費用は、夫婦が婚姻関係にある限り、原則として発生します。
この婚姻費用の分担は、現実に夫婦の間で金銭による受け渡しがなくとも、同居していれば、口座振替などで事実上で行われています。
しかし、別居しているときは婚姻費用の分担が公平に行われていないケースも見られます。
別居によって夫婦の一方が自分の実家へ戻るケースもありますが、このようなケースでは実家で生活費を負担してもらっていることがあります。
本来であれば、その生活費については夫婦の間で婚姻費用として分担すべきです。
こうしたとき、婚姻費用が必要になっていれば、配偶者に請求することも大切です。
上記のように婚姻費用の支払いを受けていない期間は婚姻費用を請求していないと見られることがあり、あとで過去分の婚姻費用を請求しても認められないこともあります。
もちろん、夫婦で話し合って過去分の婚姻費用を精算することは可能です。
しかし、夫婦の話し合いでは決まらず、家庭裁判所の調停によって請求する場合では、相手方に婚姻費用を請求した時点からの婚姻費用しか請求が認められないこともあります。
このようなことから、相手方が婚姻費用の支払いを拒んでいる場合は、早めに家庭裁判所に婚姻費用の調停を申し立てることが必要になります。
決めた婚姻費用は書面に
夫婦の間における話し合いで婚姻費用の分担方法を決めたときは、その取り決め内容を書面にしておくことも大切になります。
上記のとおり、何もしなければ、請求時点からの婚姻費用しか認められないことがあります。
いつから、いくらの婚姻費用を、どのように支払うのかについて、きちんと婚姻費用の分担契約書として残しておくと、仮に不払いが起きたときも後で請求が認められます。
また、婚姻費用に不払いがある期間は、離婚時に夫婦間で精算することもできます。
つまり、婚姻費用が不払いとなっても、その支払い約束が成立している事実が明白であれば、相手方へ請求することが可能になります。
この婚姻費用の分担方法を契約書に定める場合、未成年の子どもがあれば、子どもの監護親と他方の親との間で子どもの面会交流も合わせて定めておくことがあります。
また、婚姻費用の分担範囲を明確にしておく必要がある場合は、取り決めた具体的な使途などについて契約書に作成しておくと安全です。
このような婚姻費用の分担契約は、「契約書」「合意書」「確認書」と表題は何であっても、夫婦の間における契約書として有効になります。
もし、婚姻費用の支払期間が長期化することが見込まれたり、その金額が大きくなるときは、婚姻費用の分担を公正証書として作成しておくこともあります。
夫婦の契約は取消しできる?
夫婦の間で婚姻費用の分担方法について話し合う状況になっていると、離婚の危機に直面しているケースもあります。
婚姻関係が破たんに瀕しているときは、夫婦の間であっても大事な約束事を契約書に作成しておくことが後で意味を持つことがあります。
夫婦の契約は、婚姻期間はいつでも取り消しできることが法律に定められています。
しかし、婚姻が破たんしていたり、破たんに瀕したりしているときにした契約は、夫婦であることを理由にして取り消すことができないとされています(判例)。
「事情の変更」も考慮されます
夫婦の間で決めた婚姻費用の分担方法は、その合意をした後に夫婦の一方または双方に収入の大きな変動があったなど、合意した時から事情が変わった場合は見直しすることができます。
ただし、収入が減少すれば直ちに婚姻費用の減額が認められるものではありません。
収入変動のほか、子どもに関する支出の増加なども婚姻費用を変更する要因になります。
婚姻費用を変更するときは、夫婦であらためて協議して不公平になった分担方法を見直して、あらたに婚姻費用の分担方法を定めることになります。
婚姻費用の支払い額は、合意した時点で将来にわたり固定されるものではなく、その後に見直しされる余地のあることにも注意します。
婚姻費用等の合意書作成サポート
船橋離婚相談室は、これまで沢山の離婚相談と離婚契約書の作成に携わってきています。
別居に伴う婚姻費用の分担方法を定める合意書についても、強制執行の対象となる公正証書を作成しています。
このようなことから、ご夫婦の間に別居の問題が起きたとき、それに対応する合意書の作成をご相談いただきながらすすめることができます。
夫婦間の合意契約書を作成するとき(例)
- 夫婦が別居するに際し、婚姻費用等を取り決める。
- すでに別居中であるが、婚姻費用について取り決めていない。
- 子どもの面会交流について取り決めたい。
- 離婚する方向ですすめる意向だが、しばらくは別居して婚姻を継続する。
- 一定期間が経過した後に、婚姻を継続するか離婚するかについて協議する。
- 離婚の条件について、合意できたことを確認しておく。
直ぐに離婚しない場合にも、婚姻費用の分担方法ほか、夫婦で大事な事項を確認しておく必要がある場合があります。
このときに行なう夫婦の取り決めは、法律を踏まえて対応することが大切になります。
もし、法律上で認められない無効な取り決めをしても意味がなく、あとでトラブルが起きる原因にもなります。
また、公正証書として作成しておく場合は、定める内容を注意しなければなりません。
大事なポイントをしっかりと押さえ、将来に効果を期待できる契約書とするよう、ご利用者の方から希望条件をお伺いしたうえで、ご相談しながら契約書を作成させていただきます。
ご依頼者の方には配偶者と契約の条件について調整をしていただくことになり、完成するまでは協力してすすめていかなければなりません。
なるべくご希望にそう契約書を作成したいと考えます。
サポートのご利用料金
婚姻費用の分担方法に関する合意など、離婚も視野に入れた夫婦間における合意書を作成するサポートをご案内させていただきます。
夫婦の約束であっても、婚姻費用などの金銭の支払いに関することになれば、夫婦の間における調整などに期間を要することになります。
夫婦で話し合っても直ぐに「ハイ分かりました」というように決まらないものです。
このため、合意書作成サポートは1か月もしくは3か月のサポート保証期間を付けています。
この期間は、夫婦での調整を十分に行なっていただけるよう、ご不明な点についてのご説明や案文の修正などに丁寧に対応させていただきます。
専門家のサポートを受けながら、安心して合意書の作成をすすめていくことができます。
婚姻費用の分担等の合意書サポート
婚姻費用等の合意書作成 『安心サポート1か月プラス』 | 3万4000円(税込み) |
|---|
上記合意書の公正証書による作成 『安心サポート3か月プラス』 | 5万7000円(税込み) |
|---|
- 公正証書とする際には、上記料金のほかに公証人手数料(実費)が必要となります。公証人手数料は、公正証書に記載する契約金額などによって決まります。
- 夫婦一方側が代理人により公正証書を作成することは、公証人の了解が得られた場合に行なうことができます。
離婚協議書の作成サポート
『安心サポートプラス』の特長
夫婦の間で合意書を作成するときは、その話し合いで徐々に合意内容が固まっていきます。
大筋では決まっているように思えても、実際に合意書を作成していく段階では、内容について調整、修正が必要になる場面が多くあります。
このようなことから、決まった内容を合意書として作成するだけでなく、協議の過程における案文の修正、ご相談にも対応させていただくことで、夫婦間協議の早い段階から専門家によるサポートをご利用いただきながら協議をすすめていくことができます。
安心サポートプラスによる合意書作成は、専門家のバックアップがあることによる大きな安心感が得られることと思います。
メール・電話でも、合意書の作成、相談ができます
お忙しい、事務所まで遠いなどの理由により、フォーム、電話によるご連絡で合意書の作成をお申し込みいただく方が多くあります。
そのような方にも、支障なく合意書の完成まで対応させていただいております。
ご来所いただく方についても、初回のお申し込み時だけが普通であり、その後における連絡はメール、電話となります。
これまで全国から合意書の作成についてご依頼をいただいており、最終出来にご納得いただける合意書が完成するまで丁寧にサポートさせていただいております。
もし、ご不明点がありましら、あらかじめフォーム、お電話でご確認ください。
別居の原因となる不倫対応
配偶者の不倫が別居原因となることもあります。
そうしたとき、配偶者の不倫相手と不倫問題について整理することが必要になります。
当事務所ではそうした不倫対応についてもサポートしています。
JR船橋駅徒歩4分。土日も営業

(船橋離婚相談室内)
ご来所の相談は予約制になります
婚姻費用の合意書にかかるお打合せについて
婚姻費用の分担方法を決める状況では、別居の先にある離婚まで視野に入れて検討することも必要になります。
お電話、メールでのご利用のほか、船橋の事務所でも、婚姻費用に関するお打合せを行なうことが可能です。
船橋離婚相談室は夫婦間に起こる問題について契約書を作成するサポートをしております。
なお、事務所でのお打ち合わせは、予約制となります。
離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
- 離婚協議書
- 離婚条件を定める公正証書
- (別居時における)婚姻費用の分担契約
- 夫婦間の誓約書
- 不倫問題に対応する示談書
- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
離婚協議書作成サポートのお申し込み

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
事務所のご案内
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

運営元
船橋つかだ行政書士事務所
住所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
アクセス
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋駅から徒歩4分
ごあいさつ

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
ご利用者様の声175名
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)
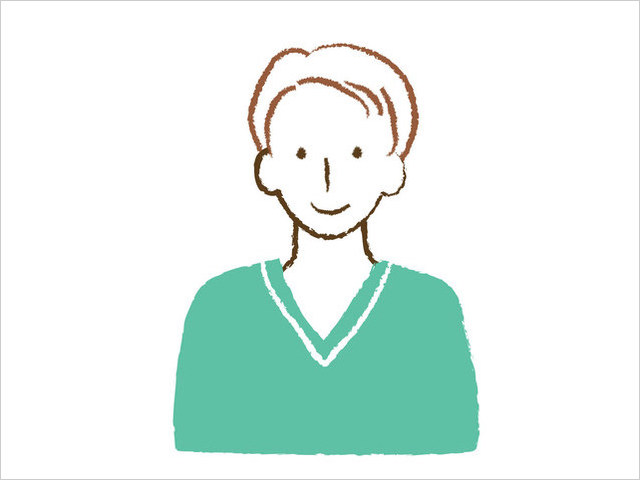
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)
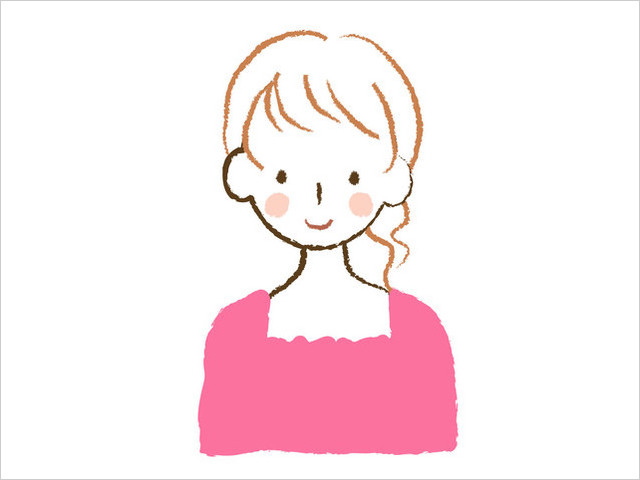
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。

