船橋ほか全国から離婚協議書・公正証書の作成(離婚相談)に対応します。土日営業・平日は夜9時まで
船橋駅4分の離婚協議書等専門の行政書士事務所<全国対応>
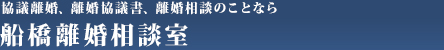
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~20時(土日9時~17時) |
|---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらから
親権監護権、面会交流、養育費などを考える
子どものことを考える

近年の調査データによりますと、未成年の子どもがある離婚は、離婚全体の6割弱の割合となっています。
両親が離婚することになれば、子どもの意思に関わりなく子どもも離婚に関わる結果となり、その影響を受けることは避けられません。
このページでは、両親が協議離婚をするとき重要になる次の3つの離婚条件について、子どもの観点から考えてみたいと思います。
離婚に関する法律書、解説本、インターネット上における情報は、当然のことですが法律的な観点若しくは夫婦の立場から離婚の手続きを中心に説明されているものがほとんどです。
それらの読者は、離婚する夫婦(両親)であり、その子どもではないからです。
それらの情報の主な内容は、離婚するための方法、その手続き、離婚時に夫婦で定める条件、注意すべき点などの説明になります。
当ウェブサイトでも協議離婚の手続きについて説明をしておりますが、このページでは、少し違った角度から整理してみたいと思います。
「子どもの側から望ましい離婚条件、離婚の形とは、どのようなものなのでしょうか?」
このようなことから、離婚における条件などについて触れていきたいと思います。
親権者と監護権者

未成年の子は、成人するまでの間、本人だけで法律行為を完結させることが基本的にできません。
法定代理人の同意を得ていない法律行為は、あとで取り消すことが認められるためです。
そこで、両親がある場合は、両親が子どもの親権者(共同親権)となり、子どもの法定代理人として子どものために法律行為を行ないます。
両親が離婚をすると、父母のどちらか一方側が親権者(単独親権)になります。
このことで親権を失くした側の親は、自分の子どもに対して親としての権利を行使することが法律上では認められなくなります。
もちろん、親子の身分関係については離婚しても法律的に変わりませんので、子どもに対して全く関与がなくなる訳ではありません。
それでも、親権を失うことになり、さらに子どもと別居することになると、親の気持ちとして本当に寂しいところでしょう。
そうしたことから、離婚に際して子どもと離れることに心の区切りを付けることができず、離婚することに同意をしても、どちらを親権者とするかを巡って夫婦では話し合いがまとまらないで家庭裁判所において調停をするケースも少なくありません。
調停により親権者の指定について夫婦で合意が成立しても、長い期間にわたって両親が親権を争ったことで父母間に大きな軋轢が生じてしまい、そのことが離婚後における面会交流の実施に悪影響が出ることもあります。
両親が離婚したときに自分のことで争いが起きたことを子どもが責任として感じてしまうと、子どもが悲しい思いをしてしまうことが心配されます。
子どもには、離婚によって一方の両親と一緒に暮らせなくなるという悲しみがあります。
子どもは、両親が離婚することになっても、できるだけ一緒に仲良く暮らしていた時の両親のイメージを損ないたくないと無意識に想うことがあります。
そもそも「親権」とは、子どもの食事や身の回りの世話をしながら一緒に生活をし、子どもの成長のために教育をしたり、子どもの財産や身分について代理をする権利のことです。
法定代理人となる親権者は、子どもにとって法律的に重要な存在となります。
父母のどちらが親権者になるかということは大変に重要なことですが、離婚した後の面会交流による子どもの精神面での成長に向けた両親による関与も考慮すると、親権を激しく争うまでになることは避けたいものです。
子どもにとっては、両方の親との関係が継続することが大切なことであり、形は変わっても、離婚後にも父母から愛情を受け続けられるとの安心感を持つことができます。
そのことが、子どもの精神面での成長に良い影響を及ぼすことになると考えます。
親権者の指定
監護者を別に分けること
子どもの親権者の指定について夫婦間の意見が合わないときに折り合いをつける方法として、親権者と監護者を別に分けることがあります。
監護権は親権の一部になります。その内容は、子どもと一緒に生活をして教育などを行なう権利であり、子どもの財産又は身分に関する代理権は含まれません。
また、監護者は、事情を考慮して例外的に子どもの祖父母などがなることもあります。
法律における基本的な考え方として、親権と監護権は一体であることを原則としているため、家庭裁判所の実務(調停など)では両者を分けることはあまり認められていません。
そうした法律上の実務からも、専門家からも分けることを勧められることはないでしょう。
親権者と別に監護者を設定すると、親権者と監護権者が共同して子どもの育成に関わることになりますので、単独親権という考えからは好まれないことになります。
ただ、親権を巡って両親が争って別れてしまい、そのことで離婚後にもう一方の親と会うこともできなくなってしまうと、子どもにとっては可哀そうなことになります。
そのことを考えれば、親権者と監護者を分けることになっても、子どもにとっては両方の親が離婚後にも自分に関わってくれていることは嬉しいことになるかもしれません。
もちろん、こうした選択をするためには、離婚後にも父母の間でコミュニケーションがある程度は良好に取れることが前提になります。
もし、父母の関係が特に悪い状況であったり、離婚原因にDV(ドメスティックバイオレンス)や虐待などがあるときには、離婚後にも大きな問題を残すことになってしまいます。
したがって、個別の事情を踏まえて判断されることになります。
基本どおりに親権と監護権を分けずに一方の親を親権・監護者にすることでも、面会交流をスムーズに実施していくことで、子ども成長のために良い環境をつくることも可能です。
子との面会交流

親権と監護権で触れましたように、離婚の成立後には両親のどちらか一方側が親権者となりますので、他方側の親は、子どもと同居できなくなります。
そうした非親権者が離婚後にも子どもと面会して親子の交流を継続することが面会交流(面接交渉)です。
面会交流は、同居できなくなった親が子どもに会えることになるとともに、子どもにとっては同居していない親にも会えることになるもので、それぞれにとって利益のあることになると考えられます。
両親から愛情または教育を受けられることは、子どもの精神面における成長にとって意義があると一般に考えられています。
しかし、現実においては、離婚協議で面会交流について定められず、離婚のあとに必ずしも面会交流が行われていないとの実態もあります。
夫婦の関係が良好でなくなった離婚する直前の時期に面会交流について話し合って取り決めることは、現実に難しい面もあります。ただ、その状況は離婚後にも変わりません。
また、DV(ドメスティックバイオレンス)を原因として離婚することになると、面会交流をすることは困難になります。
しかし、DVでなくとも面会交流を行なうことが難しいこともあります。
離婚しても父母の関係は改善しないため、子どもへの対応、教育方針などの相違から、面会をうまく実施できないこともあります。
子どもは、父母双方に親しみを持っていても、両親の微妙で難しい関係を感じ取ることで、自分の本心を素直に態度として示せないことも起きます。
本心では別居している親とも面会したいけれども、それを言うことで同居する親の機嫌が悪くなることを心配することもあります。
子どもの立場では、DVのある例外的なケースを除けば、父母双方と関わっていたいとの気持ちがあっても自然なことです。
日常生活や学校であったいろいろな出来事について、両方の親に自分の話を聞いて欲しいと思うのではないでしょうか。
自転車に乗れるようになった、鉄棒で逆上がりができるようになった、学校で友人ができた、などの報告があると思います。
そうした子どもの気持ちを出すことのできるような機会を面会交流でつくることもできます。
できるだけ無理のない範囲で面会交流を取り決めて、始めてみるのも悪くありません。
最初からキッチリと詳細な面会ルールを決めてしまっても、父母双方が決め事の実施に大きなストレスを感じることになってしまいます。
そして、そのストレスが親から子どもに伝わることで、子どもに対して良くない影響を与えてしまうことでは困ります。
また、約束を守れなかったときに、そのことが原因となって父母間にトラブルが起きると、その後に面会交流を続けていくこと難しくなってしまいます。
面会交流は、子どもの精神面における成長をたすけ、社会性を備えるうえで役立つといった、子どもの福祉の観点から実施されるものでです。
面会交流の実施面で親側にとって多少は面白くないことがあっても、子どもの成長のために、父母間で譲歩をしながら、面会交流を継続することは有益であると考えます。
夫婦の関係は離婚の成立によって解消しますが、その子にとっての父母の関係はいつまでも続いていきます。
「子のために」との観点から面会交流を考えていくことで、父母の良き思い出が子どもの心の中にいつまでも残っていくことになるのではないでしょうか。
面会交流(別居親の子への関わり)
養育費

子どもが成長して成人になるまでは、あとで短かったと感じることはありますが、現実に向き合う日々の生活としては長い年月となります。
その間には、衣食住、医療、教育などのために多くの費用がかかります。
そうした子どもの養育にかかる費用の父母間の分担として、非親権者の親から親権者の親に対して支払われるものが養育費となります。
養育費は、対象となる子どもが経済的に自立することが期待できるまで必要となりますが、家庭裁判所では基本的には20歳までとなります。
実際には、父母間の合意に基づいて、子どもが高校又は大学など学校を卒業するまで養育費を支払うことも行なわれています。
離婚時に子どもが幼いときは、子どもの将来における進学の計画も不明確ですので、ひとまず20歳までとして条件を定めておき、その後の状況に応じて変更することもできます。
子どもにとっては、別居している親からも自分のために養育費が支払われ続けていることが分かると、その親から愛されていることを感じるのではないでしょうか。
子ども成人にまで成長すれば、継続して養育費が支払われ続けてきたことの意味や重さを実感できるようになり、親に対して感謝する気持ちを持てるようになると思います。
子どもの成長にとって養育費が必要なものであることは誰にも明らかなことであるのですが、継続して養育費を受け取っている割合は現実には2割を下回っています。
養育費の支払い額は親の収入、資産等に応じて定められ、一般に毎月の定期払いになります。
ところが、はじめのうちは養育費が支払われても、途中から支払われなくなってしまうことが多く起きている現実があります。
養育費の仕組み(相場は、いつまで払う?)
支払われなくなる理由

養育費が継続して支払われなくなる理由の一つに、面会交流との関係があります。
養育費は、親が子を扶養する義務があることから支払われるものです。面会交流は、子どもの精神面における成長のために有益なものとして実施されています。
養育費の支払いも面会交流の実施も、子どものために有益なものであり、両者とも履行されることが望ましいことになります。
子どもと同居しない親は、養育費を負担し、面会交流で子どもと交流できます。親権者となる親は、養育費を受け取り、面会交流を認めることになります。
養育費と面会交流は、本来は別のことなのですが、実際には父母から「交換条件」として捉えられることがあります。
こうした事情から、「養育費を支払うから子どもに会える」「子どもに会うなら養育費を支払うべき」という主張が、父母に見られることになります。
そのため、「養育費の支払い」と「面会交流の実施」が上手くかみ合って実行されていかないと、両者とも実行されないことになってしまいます。
このようなことは、子どもからはどうなのでしょうか?
養育費が支払われなければ、子どもの家庭は経済的に厳しくなりなります。調査資料からも、母子家庭の経済状況は必ずしも良いと言えるものではありません。
面会交流の実施がされなければ、子どもは別居親との交流ができなくなります。
離婚の条件となる養育費、面会交流は、本質的には子どものために必要なものでありながら、父母の状況によって、それがなくなることも現実に起きることになっています。
父母の立場からは、子どもの幸せのために、両者が履行されることが望ましいことです。
離婚公正証書が利用される訳
子どもの幸せのために

子どもは、どうすれば幸せになるのでしょうか?
これに対する回答は難しいものです。
なぜなら、子どもが幸せであるかどうかは、それぞれ子ども本人が決めることになるからです。
子どもが未だ幼いうちであると、両親の離婚について十分に理解できないことでしょう。
しかし、いずれ大人になると、自分の周囲の状況や環境などを理解できるようになります。
そのときになれば、子ども自身で、自分の幸せを考えることになり、もし幸せであると思うならば、それまで育ててくれた両親のお蔭であると分かると思います。
世間一般では、人が幸せであるかどうかを、経済的な豊かさで測られることがあります。
その一方で、本当は、精神面における自由または豊かさが幸せを感じられるものであることを誰もが知っています。
子どもが自分を幸せであると感じられるようになるためには、そうした幸せの本質を理解できる精神面での成長を子どもの時代から育むことができたかどうかによると考えます。
子どもを精神面で健やかに成長させられるために、両親としては子どものために出来ることを行なっていくことになり、それの一部の形が、養育費や面会交流であると思います。
そういう親からの子どもへの気持ちは、子どもが大人になったときに理解してもらえるのではないでしょうか?
そうした意味では、養育費や面会交流もなく、別居親と子どもとの関わりがまったく途切れてしまうことは、子どもにとって可哀そうなことであると思います。
子どもが大人に成長したとき「お父さんありがとう」「お母さんありがとう」という感謝の気持ちを持ってもらえるよう子どもに関わっていけることは、親にも幸せであると考えます。
皆さまはどのようにお考えになられるでしょうか?
離婚の子どもへの影響

離婚した家庭の子どもにインタビューした結果をまとめた書籍(「お父さんなんかいなくても、全然大丈夫。(オープンブックス)」)があります。
こうした資料だけで、子どもの気持ちすべてを理解できるものではありませんが、少しでも理解が深められたらと読んでみました。
この本では12の離婚ケースについて、編集部が子どもに取材をしています。
当然のことですが、個々の家庭によって、それぞれの生育環境や両親の離婚事情なども違っていますので、統一的な結論めいたものはありません。
ただ、読んでみて次のことを感じました(あくまでも私的な感想です)。
- 離婚は夫婦(父母)間における理由によって起こることなので、子どもには離婚の理由が十分に理解されていない。また、親の方からも「まだ、子どもに理解できないから、詳しい理由や事情は話さない。」ということもあります。
- 家庭内で暴力を振るったりしている父親、明らかに家族に対して愛情がない父親に対して子どもは嫌悪する感情を持っている。
- 両親が喧嘩をしている姿を見ることは、子どもにとってすごく嫌な感情を抱かせ、記憶としても残ってしまう。できるだけ両親は仲良くしていて欲しいという潜在意識があるようで、離婚した後にも、いつか両親の仲が元に戻ってほしいとの願望を子どもは持つ。
- 両親が離婚しても、子どもからは父母に対して嫌いになる気持ちは持っていない。離婚後の面会交流も、暴力などの離婚事情がなければ、子どもにとって心理的な抵抗感は意外にない。それどころか、離婚しても別居する親への思慕の情は変わらない。
- 離婚してからも父母から愛情を受けることは、子どもにとって嬉しいことであり、期待もしている。
両親が離婚することの子どもへの影響を心配される向きも多いかと思います。
しかし、子ども側にも周囲の環境に順応していく能力はあり、時間の経過によって落ち着くことが見込まれます。あまり悲観的に考えることもないのではないかと考えます。
大切なことは、離婚した後にも父母がそれぞれにしっかり生きていき、子どもに対して愛情を注いでゆくことであると思います。
「離婚するときに子どものことを考える」に関連する情報
子どもの幸せとは?
離婚相談の船橋離婚相談室
ご不安を解消する離婚・不倫サポートのお問合せ
協議離婚するために離婚協議書又は公正証書を作成したい方、不倫問題への対応が必要な方の各サポートのご利用に関する相談に対応いたします。
【お願い・ご注意】
- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応には時間がかかります。そのため、ご利用者の方には各サポートで対応させていただいております。
- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、具体事例についてのアドバイスには無料相談で対応しておりません。

「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書又は公正証書、示談書などを急いで作成する必要があるときは、速やかに対応させていただきますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応いたします。
〔サポート対象となる書面〕
- 離婚協議書
- 離婚の公正証書
- 婚姻費用の分担
- 夫婦間の誓約書
- 不倫問題の示談書
- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。
*離婚情報の説明、アドバイスには対応していません。
047-407-0991
土・日も営業、平日は夜9時(電話受付は夜8時)まで営業。
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所
離婚契約書作成サポートの「離婚相談」を受付中

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書等のサポートのご利用に関することに限らせていただいております。
047-407-0991
平日9~20時(土日17時迄)
ご連絡先はこちら
離婚相談の付いた離婚協議書・離婚公正証書の作成なら
『船橋離婚相談室』

運営元
船橋つかだ行政書士事務所
住所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号
アクセス
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~20時(土日:17時)
お申込み等のご相談はこちら
船橋駅から徒歩4分
ごあいさつ

代表 塚田章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるご依頼者の方の不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかり丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
なぜ「公正証書」に?
離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
なぜ、公正証書だと
心配が解消するの?普通の離婚協議書とどう違うの?
なぜ協議離婚では公正証書が利用されるのですか?
ご利用者様の声151名
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)
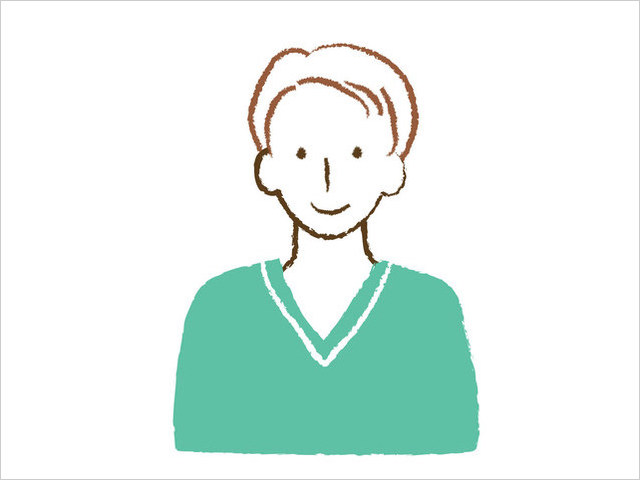
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)
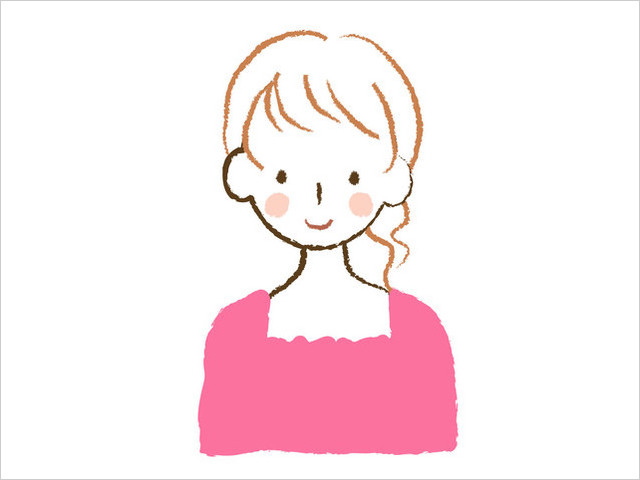
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
