離婚協議書・公正証書の作成サポート(離婚相談サービス付き)は全国からご利用いただけます。
離婚協議書作成等を専門とする船橋駅4分の行政書士事務所<全国対応>
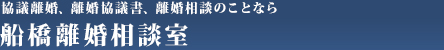
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~19時(土日9時~15時) |
|---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらへ
民法770条に定める裁判上の離婚
裁判上の離婚原因
夫婦の一方が離婚することを強く望んでいるにもかかわらず、相手方と離婚する合意が成立しないときは、家庭裁判所で離婚調停を経たうえで裁判で離婚請求することになります。
ただし、裁判で離婚請求するには、配偶者に民法770条で定める離婚原因のあること又は婚姻関係が破綻していることが必要になります。
離婚原因
夫婦間の協議で離婚する合意ができなかった場合は、家庭裁判所で離婚調停を行いますが、それでも離婚に合意ができなければ、最終的に裁判で離婚請求することになります。
裁判による方法で離婚請求するためには、配偶者の側に法律に定められた離婚原因があることが要件になります。
あるいは、別居が長く続くなど、すでに婚姻が破たんしている事実を証明します。
民法第770条では、以下の事項が裁判によって離婚請求できる離婚原因となっています。
『不貞な行為があったとき』
不貞行為は、配偶者以外の異性と性交渉する行為であり、一般に不倫、浮気とも言われます。結婚すると、夫婦それぞれは、貞操(守操)義務を負うことになり、この義務に違反することは離婚原因に当たります。
『悪意で遺棄されたとき』
遺棄とは、夫婦でたすけ合って共同生活を送ることを拒む行為が当たります。たとえば、正当な理由もないのに家から出ていったり、まったく生活費を入れない行為が当たります。
『生死が3年以上明らかでないとき』
配偶者が行方不明になってしまい、その生死が不明になった状態が3年以上も続くことです。こうした状態になれば、事実上で婚姻生活を続けることが不可能になることは明白です。
『強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき』
夫婦が協力して生活することができない程度に強い精神病に罹っているときです。ただし、離婚が認められるには、精神病になっている配偶者を放置する結果にならないよう適切な措置を講じておく必要があります。
『その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき』
家庭裁判所で個別に判断されます。たとえば、家庭内暴力(DV)がある、配偶者に無断で多額の借金を繰り返す、健康であるにもかかわらず働かない、婚姻生活を送れないまでに重度の病気に罹っている、などです。
民法第770条(裁判上の離婚)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前条第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
不貞行為

不倫、浮気と言われる、配偶者でない異性と性的関係(性交渉)をもつことを法律上で「不貞行為(ふていこうい)」と言います。
夫婦の間には貞操(守操)義務といって、夫婦以外の異性と性的関係を持たない義務があります。
したがって、この貞操義務を守らずにほかの異性と性交渉を持つことは、法律上では不法行為と捉えられ、裁判上の請求で離婚が認められることもあります。
ただし、不貞行為で婚姻関係が破たんすることで離婚が認められますので、一度でも不貞行為があれば直ちに離婚請求が認められるわけではありません。
不貞行為があっても、その不貞行為を行なった本人が深く反省しており、婚姻を継続したいとの意欲がある場合、裁判で離婚請求が認められない可能性もあります。
このほか、離婚調停、裁判が進捗しているときにも、すでに婚姻関係が破たんしているものと認められることがあります。
裁判で不貞行為を離婚原因として主張するときは、裁判所に対して不貞行為があった事実を証拠する資料が必要になります。
そのため、裁判での離婚請求においては、婚姻を継続しがたい重大事由も合わせて離婚原因として請求することが行われます。
離婚の慰謝料
不貞行為をした側からの離婚請求
不貞行為をしていた配偶者の側からも裁判による離婚請求が認められるのでしょうか?
離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないとされます。
何の落ち度もない側が有責配偶者から一方的な離婚請求を受け、それによって離婚が認められることは、社会正義に反する結果になってしまいます。
ただし、既に夫婦の別居期間が相当の長期に渡っており、婚姻が破たんしている状態にあり、夫婦に未成熟子がなく、離婚することによって離婚を求められた側の生活が経済的に困窮する恐れがない場合に限って、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。
最終的には、夫婦ごとの状況を踏まえて裁判所が判断することになります。
なお、不貞行為をされた側は、不貞行為をした配偶者とその不貞相手に対して精神的に苦痛を受けた損害賠償として慰謝料を請求することができます。
請求する慰謝料の額は、不貞行為によって被った精神的被害の程度、不貞行為をした側の経済的な負担能力などを踏まえて決められます。
不貞行為に関する慰謝料の額は、当事者間の任意交渉で決めることもできますし、裁判で請求することもできます。
なお、配偶者が不貞行為をした相手に故意(結婚している事実を知っていた)や過失(普通に注意すれば結婚している事実を知ることができた)がない場合は、慰謝料請求しても認められません。
悪意の遺棄

夫婦は、同居し、互いに協力して生活していくことが基本的な形となります。このような同居義務、生活扶助義務は法律にも定められています。
夫婦は一緒に暮らしていくものであり、どちから一方だけに給与等の経済収入があれば、その収入によって夫婦の共同生活にかかる費用を賄います。
もし、夫婦の双方が働いているときには、それぞれの収入に応じて、共同生活に必要となる費用を分担することになります。
このような当然とも言えることを夫婦の一方が故意に行わないことになれば、夫婦として共同生活していくことができなくなります。
たとえば、働いていて十分な収入があるにもかかわらず、家庭に生活費をまったく入れない、ということになれば、家計が成り立ちません。
そして、収入の少ない(又は、無い)側は、生活していくことができなくなります。
夫婦には、互いに相手と同等レベルの生活を送ることができる権利、義務があります。(これを「生活保持義務」と言います)
そのため、故意に(配偶者が困ることを知って)生活費を全く入れないという行為は、法の趣旨に反する行為になり、悪意の遺棄に当たる可能性があります。
また、夫婦として一緒に暮らしていたのに、ある日突然に何の理由もなく家から出てしまい、連絡もせず家に帰ってこない状態が続くことも、悪意の遺棄と認められる可能性があります。
このような行為は、不貞行為と同時に起こることがあります。
それは、不貞関係にある異性と一緒に生活を始めるため、夫婦で暮らす家から勝手に出ていくという事情が背景になります。
このような事態が起きると、故意に婚姻生活を一方的に放棄する行為として、悪意の遺棄に当たり裁判上の離婚原因に認められる可能性があります。
もちろん、仕事の都合上から長期間にわたって別居することになったり、夫婦双方が合意したうえで別居しているときは、悪意の遺棄には該当しません。
なお、一方が勝手に家を出ていってた場合でも、夫婦の合意で別居する場合でも、法律上の婚姻関係が継続していると、夫婦がそれぞれで生活していくための生活費を分担する義務があります。
これを、婚姻費用(こんいんひよう)の分担義務といいます。
そのため、勝手に家を出ていったような配偶者に対しても、その配偶者に収入があれば、婚姻費用の分担請求をすることができます。
婚姻関係が破綻に瀕して別居が始まると、きちんと婚姻費用が支払われないことも起こってきます。
このような場合、夫婦で協議して婚姻費用の分担方法を取り決めることが基本となりますが、協議がまとまらなければ、家庭裁判所に婚姻費用に関する調停、審判の申し立てを行って家庭裁判所で婚姻費用の分担方法を決めることになります。
同居請求
夫婦には、同居してお互いに助け合って共同生活を送る義務があります。
それは夫婦の基本的な義務になりますが、夫婦の一方が家から出ていったときには、この同居義務が問題になります。
別居することに夫婦の合意があれば良いのですが、正当な理由もないのに勝手に家を出ていくことは夫婦の同居義務違反となります。
別居期間が長くなっていくと、夫婦関係の修復を図ることが難しくなります。
別居期間は、婚姻関係の状況をはかるうえで、一つの重要な要素になります。
できるだけ早期の段階で同居を再開することを夫婦で話し合うことが必要になりますが、話し合いが上手くいかないこともあります。
このようなときは、同居を求める調停又は審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
ただし、仮に裁判所で同居を命じる審判が出されても、同居を強制することまでできません。
また、間接強制として違反した場合の金銭支払いを命じることも難しいとされています。
なお、裁判所の審判に従うことなく同居することを拒否し続けると、その行為が悪意の遺棄として離婚原因になることもあります。
夫婦で合意したうえで別居するケースもありますが、このようなことは同居義務違反に当たらないのかとの質問を受けます。
夫婦に合意があるならば、事実上で問題になることはないと思います。
ただし、合意によって別居するときは、婚姻費用の分担方法などについて、夫婦で取り決めをしておくことが大切です。
別居することは離婚に向けたステップと見られることも多く、夫婦間の約束ごとであっても、しっかり書面で確認しておくことも必要になるかもしれません。
なお、取り決めた婚姻費用の不払いが続くことになれば、離婚協議の中で清算方法を取り決めることも行なわれます。
生死不明

夫婦は一緒に生活することが基本であり、法律上においても夫婦には同居義務が課せられています。
もし、何らかの事情があって夫婦が同居できない期間があっても、必要なときには双方で連絡をとりあって夫婦関係を維持していくことが求められます。
もし、一方が家を出て行方不明になってしまい、その生死まで分からない状態になっていると、夫婦としての生活を維持することは、事実上で困難となることは明らかです。
また、行方不明となった配偶者が仮に生きていたとしても、普通ならば、その本人は婚姻を継続させたい意思を持っていないと考えられます。
このようなことから、配偶者が3年以上の期間にわたって生死が不明になっているときには、その事実は裁判上の離婚原因に該当します。
ただし、単に連絡が取れないだけであって、生きていることが分かっているときは生死不明に該当しませんので、3年以上の生死不明を要件として離婚請求しても認められません。
全く連絡を取らないまま行方をくらませていることは、夫婦における同居義務、協力扶助義務に違反することになり、「悪意の遺棄」に該当する可能性も考えられます。
なお、法律上で「失踪宣告(しっそうせんこく)」という制度があります。
この制度は、7年以上(事故等のときは1年)の間にわたり生死が不明である者については、家庭裁判所に請求することで失踪宣告をしてもらうことができます。
裁判所で失踪宣告が行なわれると、その行方不明者は死亡したとみなされます。
失踪宣告は、離婚とは異なって、相手が見つかったときには婚姻が復活することになります。
また、死亡とみなして行われた相続も無かったことになります。
裁判で離婚請求が認められると、その判決によって離婚が成立します。
しかし、その後に生死不明であった配偶者が生きて発見されたという事態も考えられます。
そうした場合、すでに離婚判決が確定していると、離婚の事実に影響はありません。
失踪宣告と離婚
配偶者が行方不明になって7年以上の長期にわたり生死不明である場合、裁判所に対して失踪宣告の申し立てができます。
そして、裁判所で失踪宣告が認められると、7年間が経過したときに申し立ての対象者は死亡したものとみなされます。
死亡したとみなされますので、配偶者が生死不明であると、配偶者は死んだものとして婚姻が解消されます。
婚姻が解消されるという点では離婚と同じですが、生きたまま別れる離婚とは異なります。
裁判上の離婚原因の一つとして「3年以上の生死不明」という事項があります。
これは、文字通りに3年以上にわたり配偶者が行方不明であるときは、裁判によって離婚請求することができるものです。期間が失踪宣告とは異なります。
離婚と失踪宣告との違いは、死亡による相続が発生するか否かということになります。
離婚では財産分与が行なわれますが、配偶者の立場での相続権は失われます。
失踪宣告では財産分与が無い代わりに相続があります。ただし、失踪宣告となってた後に本人の生存が確認されたときは、相続は取り消されます。
もっとも、3年以上の生死不明による離婚は、離婚の中でも珍しいケースであるとされます。
現実的には、7年以上の生死不明により、離婚するか失踪宣告の申し立てを行なうかの判断で迷うようなことはほとんどないのかもしれません。
強度の精神病

配偶者が強度の精神病にかかってしまうと、夫婦として精神面でのつながりが切れてしまいます。
このような状態になってしまっては、ただ看護するためだけの生活になってしまいますので、離婚することもやむを得ないものとして認められるのでしょう。
ただ、相手が強度の精神病であるならば、ただちに離婚原因として認められるというわけでもありません。
看護が必要な状態であって、夫婦としての生活が維持できなくなるまで精神病が重たいものであることが前提となります。
しかし、離婚によって病気である側が生活していけなくなる状況になってしまうと、離婚される側が困ります。
そのため、離婚した後にも療養生活を維持して、適切な治療を受けられることがある程度まで見込まれていることが必要になります。
強度の精神病にある場合は配偶者と離婚について話し合うことができませんので、協議離婚はできない状況にあります。
したがって、裁判により離婚請求していくしか方法はありません。
最終的には、精神病の重さや夫婦の生活状況、離婚したときの生活の見込みなどを踏まえて、裁判所が判断することになります。
具体的方途
配偶者がいくら不治で重度の精神病であっても、離婚した後の治療生活に見込みがついていなければ、裁判所は離婚を認めません。
そのため、離婚請求の際には、精神病の配偶者が治療生活を送ることのできる措置を確保しておくことが求められるという厳しい条件が求められます。
裁判離婚は多くありません
裁判で離婚する夫婦は、離婚全体の1~2%程度であり、かなり少ないと言えます。
夫婦の自由な意思によって婚姻したのですから、婚姻の解消についても夫婦の合意により行なうことができれば望ましいことです。
しかし、現実に裁判による離婚請求をしなければならないことには、やはり大変な事情があるものと思われます。
裁判による離婚手続になると、その準備から終結まで約1年近く期間を要すると言われます。
このような長い期間を要することが、裁判による離婚の特徴の一つになります。
また、裁判になると弁護士に事務を委任することが一般的ですので、弁護士報酬を負担しなければなりません。
裁判にかかる弁護士報酬は事務所ごとに定められており、裁判で要する弁護士報酬は着手時と裁判の終結時に発生し、そのほかに費用もかかります。
こうしたことから、裁判をするときは、上記の裁判にかかる期間と弁護士報酬の負担を踏まえたうえで、裁判により離婚する方法を選択するかどうかを検討することになります。
このようなこともあり、離婚調停にすすむことはあっても、裁判まですすむことには躊躇される方が少なくないようです。
離婚協議書(公正証書)の作成サポートのお問い合わせ
離婚協議書又は公正証書の作成サポートのお申し込み、お問い合わせに対応します。
【お願い・ご注意】
- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応については各サポートで対応させていただいております。
- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、個別事例についてのアドバイスなど一般の方に向けた無料相談には対応していません。

「ご相談しながら、離婚協議書、公正証書を作成させていただきます。よろしくお願いします。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書または公正証書、示談書などを急いで作成したい事情のある方へは、速やかに対応させていただくこともできますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、各地からのご依頼に対応します。
〔サポート対象となる契約等の書面〕
- 離婚協議書
- 離婚条件を定める公正証書
- (別居時における)婚姻費用の分担契約
- 夫婦間の誓約書
- 不倫問題に対応する示談書
- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件には対応しておりません。
こちらは行政書士事務所の電話番号です
047-407-0991
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401
船橋つかだ行政書士事務所
離婚協議書作成サポートのお申し込み

「安心できる離婚協議書をご相談しながら作成させていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書の作成など各サポートご利用契約者の方に限らせていただきます。
047-407-0991
平日9~19時(土日15時迄)
事務所のご案内
離婚相談のできる離婚協議書・公正証書の作成サポートなど
『船橋離婚相談室』

運営元
船橋つかだ行政書士事務所
住所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401
アクセス
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~19時(土日15時)
船橋駅から徒歩4分
ごあいさつ

行政書士 塚田章
日本行政書士会連合会所属
日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるうえでのご不安が軽減できるよう離婚相談を踏まえて離婚協議書(公正証書)作成を丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
ご利用者様の声175名
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)
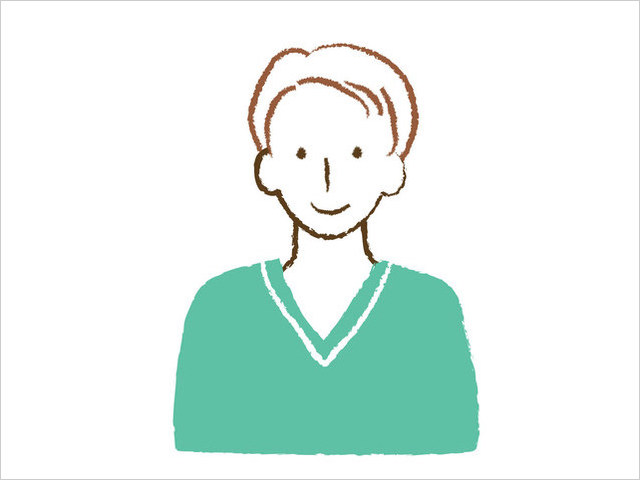
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)
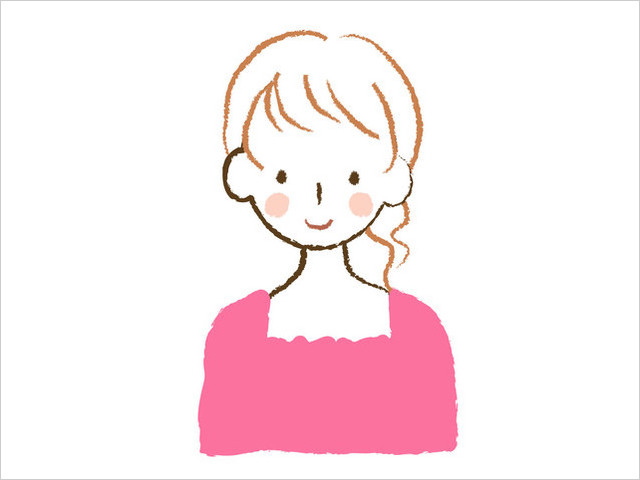
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
