船橋ほか全国から離婚協議書・公正証書の作成(離婚相談)に対応します。土日営業・平日は夜9時まで
船橋駅4分の離婚協議書等専門の行政書士事務所<全国対応>
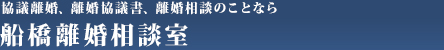
運営:船橋つかだ行政書士事務所(協議離婚・不倫対応など家事専門)
千葉県船橋市本町1丁目26-14 サンライズ船橋401号
047-407-0991
電話受付 | 平日9時~20時(土日9時~17時) |
|---|
全国からご利用いただけます
メールでのお問合せはこちらから
社会保険や各手当の申請など
離婚に伴う生活手続き
離婚した後、社会生活に関係する手続きで、速やかに行わなければならないものがあります。
また、離婚後の経済生活が厳しくなるときには生活を支援する公的扶助制度もありますので、離婚前の段階から、それらの活用も考えたうえで離婚後の生活設計を立てておきましょう。
離婚の届出までに離婚条件について夫婦で合意のできないときは、離婚後早めに協議若しくは家庭裁判所への調停の申し立てにより、大事な条件を定めておくことが大切です。
健康保険と国民健康保険

夫婦ともに企業で働いている場合は、それぞれで企業の加入する健康保険に加入してると思います。この場合には、離婚後も引き続きそれぞれの企業の健康保険に加入することになりますので変更ありません。
ただし、専業主婦又はパートをしていて夫側の健康保険の被扶養者になっていた場合は、離婚することで被扶養者ではなくなることから、離婚後は国民健康保険に加入することになります。
また、離婚後に新たに仕事に就くときは、その勤務先の健康保険に加入することもできます。
婚姻期間中は夫婦とも国民健康保険で、世帯員として加入していたときにも、離婚後には新たに世帯主として国民健康保険に加入することになります。
健康保険から国民健康保険に移動するときには、健康保険組合で発行する「資格喪失証明書」を市区町村の担当窓口へ提出することになります。
子どもがある場合は、離婚後はどちらの健康保険に加入するかを決めることになります。
同居しない親であっても、実質的な扶養者であれば、その健康保険の被扶養者のままで維持することができます。もちろん、同居する親側の保険に離婚後に移動することもできます。
国民健康保険の手続き

国民健康保険は、国民のすべてが医療保険に加入できるように、事業者の健康保険組合、共済組合保険などに加入していない人であれば誰でも加入できることになっています。
会社に勤めている方は、一般に勤務先の健康保険組合に加入しています。
でも、自営業や農業従事者の方などは会社の健康保険には加入しませんので、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険は地域単位で運営されていて、保険者は市町村になります。そのようなことから、加入手続きについても市町村の窓口で行なうことになります。
離婚後に配偶者の健康保険組合から脱退して国民健康保険に加入するときは、離婚から14日以内に市町村に加入手続きを行なうことが定められていますので、忘れずに手続きを済ませることに注意が必要です。
加入者が負担する保険料は、加入者の所得などに応じて決まります。また、一定の所得以下であると減額措置があります。
≪参考-医療保険の種類≫
全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済、国民健康保険
児童扶養手当・児童手当

両親の離婚などによって経済的に厳しい環境に置かれる児童に対して支給される手当に「児童扶養手当」があります。
18歳になる日以降の最初の3月31日までの児童に支給されます。ただし、所得による制限があります。
離婚後に子の監護養育をする母親は、この児童扶養手当を基礎収入として見込むことが多くあります。
そのため、母親は、児童扶養手当の額よりも、見込まれる養育費の額が低いことが分かると、早く離婚をした方が経済的メリットがあると考えることもあります。
ただ、児童扶養手当は、収入に応じて支給されるものであることから、あらかじめ市役所などで十分に制度の確認をしておくことが大切になります。
また、児童を育てる親に対して支給される「児童手当」があります。
こちらは、15歳になる日以降の最初の3月31日までの児童に支給されます。やはり、児童手当に関しても、所得による制限があります。
児童扶養手当の制度概要
両親の離婚などによってひとり親となった子の家庭に対して、子の生活安定と福祉のために手当(児童扶養手当)が支給される国の制度があります。
子が18歳になった以降に来る最初の3月末日まで、扶養者に支払われます。
毎年4月、8月、12月に、それまでの月分が一緒に支払われます。最大で4か月分16万円(金額は家庭によって異なります)となります。
支給手当額(月額)は、受給することになる父、母などの受給資格者の所得額や対象となる子の人数によって決められます。毎年8月時点における現況届の提出が必要になります。
〔参考-厚生労働省HPから〕
児童一人の場合 全部支給41,720円、一部支給41,710円〜9,850円
児童二人以上の加算額 二人目5,000円、三人目以降一人につき3,000円
※平成22年8月からは父子家庭の児童までも支給対象するよう制度変更が行われました。
詳しい制度内容、具体的な支給金額などにつきましては、申請の窓口となる各市区町村窓口にご確認ください。
児童手当の制度概要
日本国内に住んでいて児童のいる家庭に対して、児童が中学校を修了するまでの間に支払われる手当が、児童手当です。
離婚前に別居している夫婦については、児童と同居している方の親に対して支給されます。
〔手当額〕
- 0〜3歳未満 15,000円
- 3歳〜小学校終了 第1子、第2子10,000円(第3子以降15,000円)
- 中学生 10,000円
- 所得制限※以上になると5,000円
※所得制限限度額<参考:平成25年5月分まで>
平成23年の扶養親族の数と所得制限限度額
0人のとき、622万円、1人のとき、660万円、2人のとき、698万円、3人のとき、736万円
〔支払時期〕
- 毎年2月、6月、10月
児童手当は、収入額によっては児童扶養手当と合わせて受給することも可能になります。
詳しい制度の内容については、市区町村窓口まで直接ご確認ください。
母子福祉資金
配偶者がなく児童を扶養している女性に対して、事業開始資金、修業資金、生活資金、修学支度資金などを、自治体が無利子又は低利で貸し付ける制度として「母子福祉資金の貸付制度」があります。
離婚後に資金が必要なときには、一応の検討をされてみては良いのではないかと考えます。
母子福祉資金の制度概要
母子家庭の経済的自立と児童の福祉向上を図るために、事業、修学などに必要となる資金について、無利子または低利子で貸し付ける制度があります。
≪参考-千葉県の例≫
〔貸付け対象〕
- 20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母
- 父母のいない20歳未満の児童
〔保証人〕
- 原則65歳未満で県内に居住し、独立生計を営んでいる保証人1名
〔貸付金の種類(限度額)〕
- 事業開始資金(283万)
- 事業継続資金(142万)
- 修学資金・高校専修学校(国公立月額1.8万、私立月額3万)
- 修学資金・大学(国公立月額4.5万、私立月額5.4万)
- その他あり
※詳しくは、地元自治体まで直接ご確認ください。
離婚条件に合意の成立していないとき
離婚する際に、早く離婚することを優先して進めた結果、離婚に関する条件について、相手と十分に話し合っておらず、いまだ合意に至っていないケースが多くあります。
このようなとき、離婚後であっても、相手と協議をすすめて、大事な離婚条件については定めておいた方が安心です。
しかし、離婚後になるとお互いが別居していることもあり、離婚条件について話し合いをする機会を持つことも、なかなか容易ではなくなります。
そのため、書面等による連絡で協議することもあります。
夫婦に子どもがあるとき、養育費は離婚後ただちに必要になるものですから、早めに相手に対し協議することを申し出て、養育費の負担額、方法を定めます。
もし、協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停、審判を申し立て、そこで養育費を定めることになります。
養育費以外にも、財産分与を決める必要があるときには、早めに協議を開始します。
財産分与は、離婚から2年以内しか請求できる期間がありません。そのため、財産分与を受けられる財産があるのであれば、相手に対して財産分与の請求をすべきです。
財産分与についても当事者間の協議で決まらないときには、家庭裁判所へ調停または審判を申し立てることができます。
離婚条件について当事者間だけで合意ができれば、離婚後でも、離婚協議書、離婚公正証書を作成することができます。
請求権がなくなる
離婚後にも財産分与などの取り決めはできます。ただ、いつまでも不安定な権利関係を続かせることは良くありませんので、これらの請求権には期限があります。
財産分与、年金分割は、離婚から2年以内に請求することが求められ、慰謝料請求は、離婚から3年以内となります。
時間の経過により財産が散逸したり、記録、記憶なども曖昧になってきますので、協議はできるだけ早めに開始されることが勧められます。
各種手続きの事前確認
離婚する際には、多くの整理事項、手続きが一度にでてきます。さらに、離婚時に住居の引っ越しが重なると、各種の届出も重なります。
気持ちのうえであまり余裕はないものですが、必要な手続はどのようなことがあるのか事前に押さえておいて、可能な範囲で書類などを準備もしておくこともが安全です。
手続に漏れの生じないように、あらかじめ、やるべき手続のリストを作成しておくことを、お勧めします。
離婚後の生活手続き
離婚相談の船橋離婚相談室
ご不安を解消する離婚・不倫サポートのお問合せ
協議離婚するために離婚協議書又は公正証書を作成したい方、不倫問題への対応が必要な方の各サポートのご利用に関する相談に対応いたします。
【お願い・ご注意】
- 協議離婚の各条件と仕組み、不倫対応の流れ、注意すべき事項、他事例の紹介、アドバイスなどの具体的なご相談、説明の対応には時間がかかります。そのため、ご利用者の方には各サポートで対応させていただいております。
- 業務上の都合から、養育費又は慰謝料の額、具体事例についてのアドバイスには無料相談で対応しておりません。

「ご相談しながら、希望する離婚協議書を作成させていただきます。お気軽にお電話ください。」
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
離婚協議書又は公正証書、示談書などを急いで作成する必要があるときは、速やかに対応させていただきますので、ご相談ください。
お電話又はメールだけでのご利用方法も可能ですので、全国からのご依頼に対応いたします。
〔サポート対象となる書面〕
- 離婚協議書
- 離婚の公正証書
- 婚姻費用の分担
- 夫婦間の誓約書
- 不倫問題の示談書
- 慰謝料、養育費の請求書(内容証明郵便)
*こちらは離婚協議書、公正証書等の作成をサポートする事務所になります。
*離婚調停、紛争案件についてのご質問・相談には対応しておりません。
*離婚情報の説明、アドバイスには対応していません。
047-407-0991
土・日も営業、平日は夜9時(電話受付は夜8時)まで営業。
JR船橋駅、京成船橋駅、東武船橋駅から徒歩4分
千葉県船橋市本町1-26-14 サンライズ船橋401号 船橋つかだ行政書士事務所
離婚契約書作成サポートの「離婚相談」を受付中

「ご不安を解消する離婚契約書を作成するお手伝いをさせていただきます。」
〔離婚相談について〕
離婚協議書等のサポートのご利用に関することに限らせていただいております。
047-407-0991
平日9~20時(土日17時迄)
ご連絡先はこちら
離婚相談の付いた離婚協議書・離婚公正証書の作成なら
『船橋離婚相談室』

運営元
船橋つかだ行政書士事務所
住所
千葉県船橋市本町1-26-14
サンライズ船橋401号
アクセス
船橋駅(JR・京成・東武)
徒歩4分
047-407-0991
平日9時~20時(土日:17時)
お申込み等のご相談はこちら
船橋駅から徒歩4分
ごあいさつ

代表 塚田章
日本行政書士会連合会所属
特定行政書士
日本カウンセリング学会員
JADP認定上級心理カウンセラー
ごあいさつ
船橋離婚相談室の塚田です。
協議離婚をすすめるご依頼者の方の不安が少しでも解消できるよう、離婚相談から離婚協議書の作成まで、しっかり丁寧にサポートさせていただきます。安心してご利用ください。
なぜ「公正証書」に?
離婚協議書を、
公正証書に作成すると・・
なぜ、公正証書だと
心配が解消するの?普通の離婚協議書とどう違うの?
なぜ協議離婚では公正証書が利用されるのですか?
ご利用者様の声151名
離婚協議書(離婚公正証書)サポートのご利用者様によるアンケート回答のご案内です
30歳代、女性
(離婚協議書作成プラン)

案文作成の段階から主人側と内容についてぶつかり困っていました・・・
50歳代、男性、子1人
(離婚協議書作成プラン)
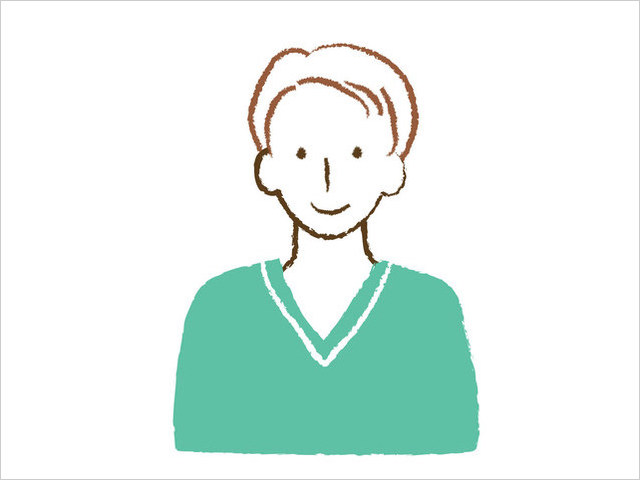
作成したことにより、財産分与、特に年金についての扱いについて安心・・・
40歳代、女性、子2人
(離婚公正証書作成)
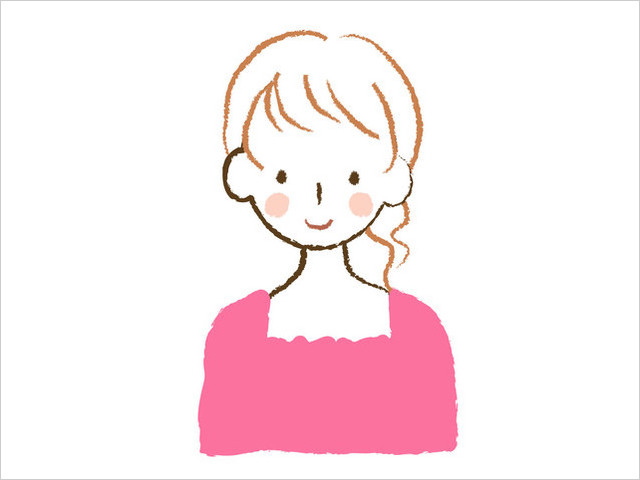
離婚届けを提出する前に、各々の条件を十分に話し合い、それを文章に・・・
30歳代、男性、子2人(離婚公正証書作成)

公証役場で公証人を離婚後のするだけでも心が引き締り・・・
協議離婚における離婚協議書の利用事例として、ご参考にしていただければ幸いです。
